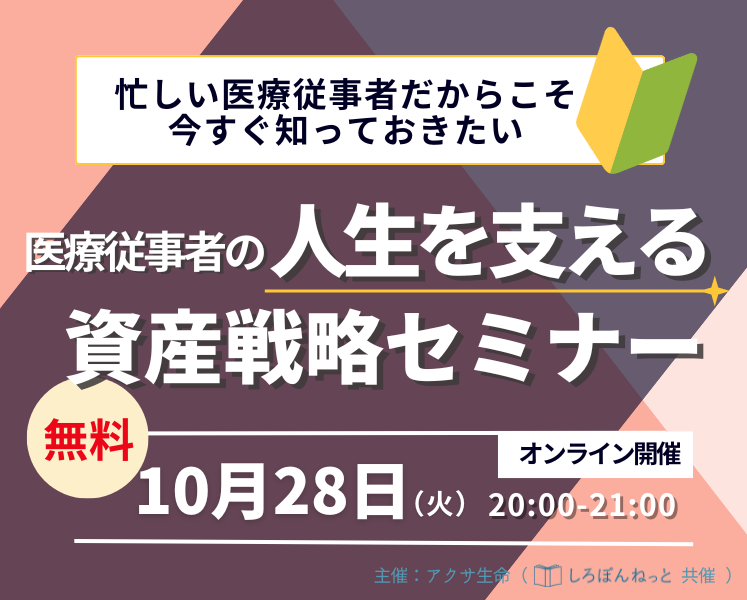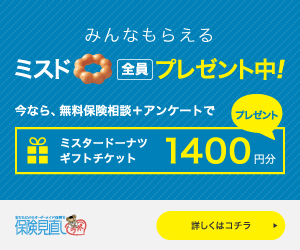ファセンラ皮下注30mgペン

添付文書情報2025年03月改定(第4版)
商品情報
- 習
- 処
- 生
- 特生
- 特承
- 毒
- 劇
- 麻
- 覚
- 覚原
- 向
- 禁忌
- 2.1. 本剤及び本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。
- 効能・効果
- 1). 気管支喘息(既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る)。
2). 既存治療で効果不十分な好酸球性多発血管炎性肉芽腫症。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈気管支喘息〉高用量の吸入ステロイド薬とその他の長期管理薬を併用しても、全身性ステロイド薬の投与等が必要な喘息増悪をきたす患者に本剤を追加して投与すること。
5.2. 〈気管支喘息〉投与前の血中好酸球数が多いほど本剤の気管支喘息増悪発現に対する抑制効果が大きい傾向が認められており、また、データは限られているが、気管支喘息で投与前の血中好酸球数が少ない患者では、十分な気管支喘息増悪抑制効果が得られない可能性があるので、本剤の作用機序及び臨床試験で認められた投与前の血中好酸球数と有効性の関係を十分に理解し、患者の血中好酸球数を考慮した上で、適応患者の選択を行うこと〔17.1.1参照〕。
5.3. 〈気管支喘息〉本剤は既に起きている気管支喘息の発作や症状を速やかに軽減する薬剤ではないため、急性の発作に対しては使用しないこと。
5.4. 〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉過去の治療において、全身性ステロイド薬による適切な治療を行っても、効果不十分な場合に、本剤を上乗せして投与を開始すること。
- 用法・用量
- 〈気管支喘息〉
通常、成人、12歳以上の小児及び体重35kg以上の6歳以上12歳未満の小児にはベンラリズマブ(遺伝子組換え)として1回30mgを、初回、4週後、8週後に皮下に注射し、以降、8週間隔で皮下に注射する。
〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉
通常、成人にはベンラリズマブ(遺伝子組換え)として1回30mgを4週間隔で皮下に注射する。
(用法及び用量に関連する注意)
7.2. 〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉本剤とシクロホスファミドを併用投与した場合の安全性は確認されていない〔17.1.3参照〕。
- 合併症・既往歴等のある患者
- 8.1. 〈効能共通〉本剤の投与は、適応疾患の治療に精通している医師のもとで行うこと。
8.2. 〈効能共通〉本剤の投与開始後にステロイド薬を急に中止しないこと(ステロイド薬の減量が必要な場合には、医師の管理下で徐々に行うこと)。
8.3. 〈効能共通〉本剤はヒトインターロイキン-5(IL-5)受容体αサブユニットと結合することにより、好酸球数を減少させるが、好酸球は一部の寄生虫(蠕虫)感染に対する免疫応答に関与している可能性があるので、患者が本剤投与中に寄生虫感染し、抗寄生虫薬による治療が無効な場合には、本剤投与の一時中止を考慮すること〔9.1.1参照〕。
8.4. 〈効能共通〉本剤の投与によって合併する他の好酸球関連疾患の症状が変化する可能性があり、当該好酸球関連疾患に対する適切な治療を怠った場合、症状が急激に悪化し、喘息等では死亡に至るおそれもある。本剤の投与間隔変更後及び投与中止後の疾患管理も含めて、本剤投与中から、合併する好酸球関連疾患を担当する医師と適切に連携すること。患者に対して、医師の指示なく、合併する他の好酸球関連疾患に対する治療内容を変更しないよう指導すること。
8.5. 〈気管支喘息〉本剤の投与開始後に喘息症状がコントロール不良であったり、悪化した場合には、医師の診療を受けるように患者に指導すること。
8.6. 〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉本剤の投与開始にあたっては、医療施設において、必ず医師によるか、医師の直接の監督のもとで投与を行うこと(自己投与の適用
については、医師がその妥当性を慎重に検討し、十分な教育訓練を実施した後、本剤投与による危険性と対処法について患者が理解し、患者自ら確実に投与できることを確認した上で、医師の管理指導のもとで実施すること)。自己投与の適用後、本剤による副作用が疑われる場合や自己投与の継続が困難な状況となる可能性がある場合には、直ちに自己投与を中止させ、医師の管理のもとで慎重に観察するなど適切な処置を行うこと。また、自己投与の適用後、本剤投与後に副作用の発現が疑われる場合は、医療施設へ連絡するよう患者に指導を行うこと。使用済みの注射器を再使用しないように患者に注意を促し、すべての器具の安全な廃棄方法に関する指導を行うと同時に、使用済みの注射器を廃棄する容器を提供すること。
9.1.1. 寄生虫に感染している患者:本剤の投与開始前に寄生虫感染を治療すること〔8.3参照〕。
- 副作用
- 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 重大な副作用
- 11.1. 重大な副作用
重篤な過敏症(頻度不明):アナフィラキシー(蕁麻疹、血管浮腫、喉頭浮腫、アナフィラキシー反応等)等の重篤な過敏症があらわれることがある。また、過敏症反応の発現が遅れて認められることがある。
- 11.2. その他の副作用
1). 精神神経系:(1%以上10%未満)頭痛。
2). 感染症:(頻度不明)咽頭炎(咽頭炎、細菌性咽頭炎、ウイルス性咽頭炎、及びレンサ球菌性咽頭炎)。
3). 全身障害:(1%以上10%未満)発熱。
4). 投与部位:(1%以上10%未満)注射部位反応(疼痛、紅斑、そう痒感、丘疹等)。
5). 過敏症:(0.1%以上1%未満)過敏症反応(蕁麻疹、丘疹状蕁麻疹、及び発疹)。
- 高齢者
- 一般的に生理機能が低下している。
- 授乳婦
- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること(本剤はモノクローナル抗体であり、動物実験(カニクイザル)において本剤は胎盤を通過することが報告されており、妊娠中のカニクイザルにおける曝露量が臨床投与量における曝露量の99.0倍であったときに、出生仔末梢血好酸球減少が認められたが、出生後180日までに回復した)。
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること(本剤の乳汁中への移行は不明である)。
- 小児等
- 9.7.1. 〈気管支喘息〉気管支喘息の6歳未満の幼児等を対象とした臨床試験は実施していない。
9.7.2. 〈好酸球性多発血管炎性肉芽腫症〉好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の小児等を対象とした臨床試験は実施していない。
- 取扱い上の注意
- 14.1. 薬剤投与前の注意14.1.1. 投与30分前に冷蔵庫から取り出し、本剤を外箱に入れたままの状態で室温に戻しておくことが望ましい。
14.1.2. 使用前に不溶性異物や変色がないことを目視により確認する(不溶性異物又は変色が認められる場合は使用しない)。
14.2. 薬剤投与時の注意14.2.1. 皮膚に圧痛・挫傷・紅斑・硬化がある部位には使用しないこと。
14.2.2. 投与部位は、上腕部、大腿部又は腹部とすること。同一箇所へ繰り返し注射することは避け、投与毎に注射部位を変えること。
14.2.3. 本剤は、1回使用の製剤であり、再使用しないこと。
20.1. 本剤は激しく振とうしないこと。
20.2. 本剤は凍結を避け、凍結した場合は使用しないこと。
20.3. 光曝露を避けるため、本剤は外箱に入れて保存すること。
20.4. 冷蔵庫から出した後は30℃以下で保存し、14日以内に使用すること。
- その他の注意
- 15.1. 臨床使用に基づく情報重症喘息患者を対象とした第3相国際共同臨床試験(SIROCCO試験及びCALIMA試験)において、本剤の成人の気管支喘息における承認用法・用量で投与を受けた患者の14.9%(122/820例)に抗ベンラリズマブ抗体が認められ、12.0%(98/820例)に中和抗体が認められた。小児の重症喘息患者を対象として薬物動態、薬力学及び長期安全性を評価した第3相国際共同試験(TATE試験)において、6~14歳の重症喘息患者の13.3%(4/30例)に抗ベンラリズマブ抗体が認められ、4例全てに中和抗体が認められた。好酸球性多発血管炎性肉芽腫症患者を対象とした第3相国際共同臨床試験(MANDARA試験)において、9.0%(6/67例)に抗ベンラリズマブ抗体が認められ、1.5%(1/67例)に中和抗体が認められた。抗ベンラリズマブ抗体陽性となった一部の患者では、血清中ベンラリズマブ濃度低下及び本剤投与後に減少した血中好酸球数増加が認められた。なお、抗ベンラリズマブ抗体の発現による本剤の有効性及び安全性に対する影響を示唆する成績は得られていない。
16.1 血中濃度
16.1.1 単回投与
日本人健康成人に本剤25、100及び200mg注)を単回皮下投与したときの血清中濃度推移及び薬物動態パラメータは次記のとおりである。
図1 日本人健康成人における血清中濃度推移(平均値+標準偏差)
表1 日本人健康成人における単回皮下投与時の薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
注)本剤の成人の気管支喘息及び好酸球性多発血管炎性肉芽腫症における承認用量は1回30mgである。
日本人小児喘息患者に本剤10及び30mgを単回皮下投与したときの血清中濃度推移及び薬物動態パラメータは次記のとおりである。
図2 日本人小児喘息患者における血清中濃度推移(平均値±標準偏差)
表2 日本人小児喘息患者における単回皮下投与時の薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
16.1.2 反復投与
第III相国際共同試験(CALIMA試験)において、本剤の成人の気管支喘息における承認用法・用量で投与を受けた喘息患者(日本人患者を含む)の投与開始後16週及び48週の血清中トラフ濃度(平均値±標準偏差、以下同様)は、それぞれ412±330ng/mL(377例)及び326±267ng/mL(337例)であった。これらの患者のうち、日本人集団における投与開始後16週及び48週の血清中トラフ濃度は、それぞれ452±324ng/mL(26例)及び392±326ng/mL(26例)であった。
第III相国際共同試験(MANDARA試験)において、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症における本剤の承認用法・用量で投与を受けた好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の患者(日本人患者を含む)の投与開始後12週及び52週の血清中トラフ濃度は、それぞれ1998±902ng/mL(66例)及び2101±1098ng/mL(62例)であった。
16.2 吸収
母集団薬物動態解析の結果、上腕部への皮下投与時の絶対的バイオアベイラビリティは58.9%と推定された。
16.4 代謝
ベンラリズマブはヒト化IgG1モノクローナル抗体であり、肝臓以外にも広く生体に存在するタンパク質分解機構により消失すると推定される。
17.1 有効性及び安全性に関する試験
17.1.1 第III相国際共同試験(CALIMA試験)(成人及び12歳以上の小児)
中用量又は高用量の吸入ステロイド(ICS)及び長時間作用性β2刺激薬(LABA)で治療してもコントロール不良の成人又は小児(12歳以上、海外のみ)喘息患者1,306例(日本人患者83例を含む)を対象としたランダム化、プラセボ対照、二重盲検、並行群間比較国際共同試験を実施した。中用量又は高用量ICS/LABAの併用下で、本剤30mg又はプラセボを、4週に1回(Q4W)、又は最初の3回は4週に1回、以降8週に1回(Q8W)、56週間皮下投与した。有効性の主要解析対象集団である高用量ICS/LABAを使用しているベースラインの血中好酸球数が300/μL以上の被験者において、主要評価項目である年間喘息増悪率(モデル調整済み)は、本剤Q8W群、プラセボ群でそれぞれ0.66、0.93であり、プラセボ群と比較して本剤Q8W群で有意に低下した(表3)。
表3 年間喘息増悪率(高用量ICSを使用しているベースラインの血中好酸球数300/μL以上の集団)
→図表を見る(PDF)
有効性の主要解析対象集団のうち、日本人集団における年間喘息増悪率の解析結果を表4に示した。
表4 日本人集団における年間喘息増悪率(高用量ICSを使用しているベースラインの血中好酸球数300/μL以上の集団)
→図表を見る(PDF)
また、ベースラインの血中好酸球数別の年間喘息増悪率の部分集団別解析結果は表5のとおりであった。[5.2参照]
表5 ベースラインの血中好酸球数別の年間喘息増悪率のプラセボ群との比(高用量ICSを使用している集団)
→図表を見る(PDF)
本剤30mg Q8W群における副作用発現頻度は12.6%(54/428例)であり、主な副作用は、頭痛1.4%(6/428例)、次いで発熱1.2%(5/428例)であった。
17.1.2 第III相国際共同試験(TATE試験)(6歳以上14歳以下の小児)
血中好酸球数が試験開始時に150/μL以上、かつ中用量又は高用量ICS及びLABA等のその他の長期管理薬で治療しても喘息増悪をきたす6~11歳(6~14歳、日本のみ)の小児喘息患者30例(日本人患者11例を含む)を対象とした非盲検、並行群間国際共同試験を実施した注1)。中用量又は高用量のICS及びその他の長期管理薬併用下で、本剤10又は30mg注2)を、最初の3回は4週に1回(Q4W)、以降の4回は8週に1回(Q8W)、48週間皮下投与した。6~14歳の患者における副作用発現頻度は13.3%(4/30例)であり、報告された副作用は頭痛、疲労、注射部位反応及び消化不良が各3.3%(1/30例)であった。
注1)本試験の目的は、ベンラリズマブ皮下投与時の薬物動態、薬力学及び長期安全性の評価であった。
注2)体重が35kg未満の6~11歳の患者には本剤10mgを投与した。体重が35kg以上の6~11歳の患者又は12~14歳の患者には本剤30mgを投与した。
17.1.3 第III相国際共同試験(MANDARA試験)
再燃又は難治性の好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の成人患者140例(日本人患者8例を含む)を対象としたランダム化、実薬対照、二重盲検、非劣性国際共同試験を実施した。本試験の二重盲検投与期では、経口ステロイド薬(プレドニゾロン換算で7.5~50mg/日)注1)に追加注2)して、本剤30mg Q4W、又はメポリズマブ300mg Q4Wを52週間皮下投与した。主要評価項目である投与開始後36週及び48週の両方で寛解(経口ステロイド薬4mg/日[プレドニゾロン換算]以下かつBirmingham Vasculitis Activity Score[BVAS]=0)を達成した被験者の割合における本剤群とメポリズマブ群の群間差は、1.21%(95%信頼区間:-14.11、16.53)であり、信頼区間の下限が予め設定していた非劣性マージン-25%を超えた(表6)。投与開始後48~52週で経口ステロイド薬の平均1日用量をベースラインから100%減量できた被験者の割合は本剤群で41%、メポリズマブ群で26%であった。また、ベースラインから50%以上減量できた被験者の割合は本剤群で84%、メポリズマブ群で74%であった。[7.2参照]
注1)経口ステロイド薬は、医師の判断で投与開始4週以降に適宜減量することと設定した。
注2)免疫抑制剤(シクロホスファミドを除く)は、併用可能とされた。
表6 寛解を達成した被験者の例数及び割合
→図表を見る(PDF)
二重盲検投与期の本剤群における副作用発現頻度は28.6%(20/70例)であり、主な副作用(3%以上)は、頭痛7.1%(5/70例)、次いで注射部位疼痛4.3%(3/70例)であった。
18.1 作用機序
本剤は、ヒトインターロイキン‐5受容体αサブユニット(IL‐5Rα)に特異的かつ高親和性で結合(解離定数:16pM)する、フコース欠損型ヒト化免疫グロブリンGサブクラス1、κ型アイソタイプ(IgG1κ)モノクローナル抗体である。
18.2 アポトーシス誘導作用
本剤は、Fcドメインのフコース欠損により、ナチュラルキラー細胞等のエフェクター細胞上のFcγRIIIaに高い親和性(解離定数:45.5nM)を示すために抗体依存性細胞傷害活性が増強され、IL‐5Rαを発現する好酸球及び好塩基球のアポトーシスを誘導する。
18.3 血中好酸球の除去作用
第III相国際共同試験(SIROCCO試験及びCALIMA試験)で、成人の気管支喘息における承認用法・用量で本剤を皮下投与したとき、及び第III相国際共同試験(TATE試験)で、6~14歳の小児の気管支喘息における承認用法・用量で本剤を皮下投与したときに血中好酸球の低下が認められた。同様の血中好酸球の低下が、第III相国際共同試験(MANDARA試験)で、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症における承認用法・用量で本剤を皮下投与したときにも認められた。
- 製造販売会社
- アストラゼネカ
- 販売会社
おくすりのQ&A
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。