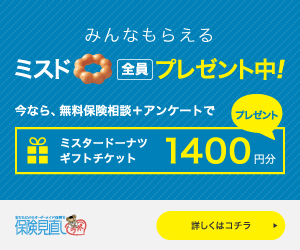エフメノカプセル100mg

添付文書情報2025年01月改定(第4版)
商品情報
- 禁忌
- 2.1. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。
2.2. 診断未確定の性器出血のある患者[病因を見のがすおそれがある]〔8.1参照〕。
2.3. 重度肝機能障害のある患者〔9.3.1参照〕。
2.4. 乳癌の既往歴又は疑いがある患者[症状が悪化するおそれがある]〔8.1、9.1.6、15.1.1参照〕。
2.5. 生殖器癌の既往歴又は疑いがある患者[症状が悪化するおそれがある]〔15.1.5参照〕。
2.6. 動脈血栓塞栓症又は静脈血栓塞栓症あるいは重度血栓性静脈炎の患者又は既往歴のある患者[症状が悪化するおそれがある]〔11.1.1、15.1.2、15.1.3参照〕。
2.7. 脳出血のある患者[症状が悪化するおそれがある]〔11.1.1参照〕。
2.8. ポルフィリン症の患者[症状が悪化するおそれがある]。
- 効能・効果
- 更年期障害及び卵巣欠落症状に対する卵胞ホルモン剤投与時の子宮内膜増殖症の発症抑制。
(効能又は効果に関連する注意)
本剤は、子宮のない患者には投与しないこと。
- 用法・用量
- 卵胞ホルモン剤との併用において、次のいずれかを選択する。
・ 卵胞ホルモン剤の投与開始日からプロゲステロンとして100mgを1日1回就寝前に経口投与する。
・ 卵胞ホルモン剤の投与開始日を1日目として、卵胞ホルモン剤の投与15日目から28日目までプロゲステロンとして200mgを1日1回就寝前に経口投与する。これを1周期とし、以後この周期を繰り返す。
(用法及び用量に関連する注意)
食後に本剤を投与した場合、Cmax上昇及びAUC上昇するとの報告がある。食事の影響を避けるため、食後の服用は避けること〔16.2参照〕。
- 肝機能障害患者
- 8.1. 投与前に病歴、家族素因等の問診、乳房検診並びに婦人科検診(子宮内膜細胞診及び超音波検査による子宮内膜厚の測定を含む)を行い、投与開始後は定期的に乳房検診並びに婦人科検診を行うこと〔2.2、2.4、9.1.6、15.1.1参照〕。
8.2. 外国において、卵胞ホルモン剤と黄体ホルモン剤を長期併用した女性では、乳癌になる危険性がホルモン補充療法(HRT)未実施群の女性と比較して高くなり、その危険性は併用期間が長期になるに従って高くなるとの報告があるので、本剤の使用にあたっては、患者に対し本剤のリスクとベネフィットについて十分な説明を行うとともに必要最小限の使用にとどめ、漫然と長期使用を行わないこと〔15.1.1参照〕。
8.3. 本剤の服用により、血栓症があらわれることがあるので、次のような症状・状態があらわれた場合は投与を中止すること。また、患者に対しては、血栓症の初期症状、血栓症のリスクが高まる状態が認められた場合には直ちに医師等に相談するよう、あらかじめ説明すること〔9.1.7、11.1.1参照〕。
・ 血栓症の初期症状:下肢疼痛・下肢浮腫、突然の呼吸困難、息切れ、胸痛、中枢神経症状(めまい、意識障害、四肢麻痺等)、急性視力障害等。
・ 血栓症のリスクが高まる状態:体を動かせない状態、顕著な血圧上昇がみられた場合等。
8.4. 投与の中止により、不安、気分変化、発作感受性の増大を引き起こす可能性があるので、投与中止の際には注意するよう患者に十分説明すること。
8.5. 傾眠状態や浮動性めまいを引き起こすことがあるので、自動車の運転等、危険を伴う機械の操作に従事する際には注意するよう患者に十分説明すること。
9.1.1. てんかん又はその既往歴のある患者:副腎皮質ホルモン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある。
9.1.2. うつ病又はその既往歴のある患者:注意深く観察し、うつ病症状悪化を認めた場合は投与を中止するなど注意すること(副腎皮質ホルモン様作用により病態に影響を及ぼすおそれがある)。
9.1.3. 片頭痛、喘息又はその既往歴のある患者:病態に影響を及ぼすおそれがある。
9.1.4. 心機能障害のある患者:体液貯留を引き起こすおそれがある。
9.1.5. 糖尿病の患者:糖尿病が悪化するおそれがある。
9.1.6. 乳癌家族素因が強い患者、乳房結節のある患者、乳腺症の患者又は乳房レントゲン像に異常がみられた患者:症状を悪化させるおそれがある〔2.4、8.1参照〕。
9.1.7. 術前又は長期臥床状態の患者:血液凝固能が亢進され、心血管系の副作用
の危険性が高くなることがある〔8.3、11.1.1参照〕。
腎機能障害患者:体液貯留を引き起こすおそれがある。
9.3.1. 重度肝機能障害のある患者:投与しないこと(作用が増強されるおそれがある)〔2.3参照〕。
9.3.2. 中等度以下の肝機能障害のある患者:作用が増強されるおそれがある。
- 相互作用
- 10.2. 併用注意:肝酵素誘導剤、抗てんかん薬(フェノバルビタール、フェニトイン、カルバマゼピン等)、リファンピシン[本剤の作用を減弱させることがある(これらの薬物の肝薬物代謝酵素誘導作用による)]。
- 副作用
- 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 重大な副作用
- 11.1. 重大な副作用
11.1.1. 血栓症(頻度不明):心筋梗塞、脳血管障害、動脈血栓塞栓症又は静脈血栓塞栓症(静脈血栓塞栓症又は肺塞栓症)、血栓性静脈炎、網膜血栓症があらわれたとの報告がある〔2.6、2.7、8.3、9.1.7参照〕。
- 11.2. その他の副作用
1). 心臓障害:(0.1~1%未満)動悸、右脚ブロック、洞性不整脈。
2). 耳及び迷路障害:(1%以上)回転性めまい。
3). 眼障害:(0.1~1%未満)眼充血、眼瞼皮膚乾燥、(頻度不明)視覚障害。
4). 胃腸障害:(1%以上)下腹部痛、腹部膨満、便秘、悪心、腹部不快感、(0.1~1%未満)上腹部痛、腹痛、軟便、下痢、口唇乾燥、口腔内不快感、痔核、舌痛、(頻度不明)嘔吐。
5). 肝胆道系障害:(頻度不明)胆汁うっ滞性黄疸。
6). 一般・全身障害及び投与部位の状態:(1%以上)末梢性浮腫、(0.1~1%未満)異常感、口渇、顔面浮腫、胸痛、胸部不快感、倦怠感、熱感、発熱、末梢腫脹。
7). 感染症及び寄生虫症:(0.1~1%未満)外陰部腟カンジダ症、毛包炎。
8). 臨床検査:(0.1~1%未満)ALP上昇、CK上昇、脂質増加、白血球数増加、γ-GTP増加。
9). 代謝及び栄養障害:(0.1~1%未満)食欲減退、食欲亢進。
10). 筋骨格系及び結合組織障害:(1%以上)背部痛、(0.1~1%未満)関節腫脹、四肢不快感。
11). 良性、悪性及び詳細不明の新生物(嚢胞及びポリープを含む):(0.1~1%未満)子宮平滑筋腫。
12). 神経系障害:(1%以上)頭痛、浮動性めまい、傾眠、(0.1~1%未満)感覚鈍麻、神経痛、注意力障害、頭部不快感。
13). 精神障害:(0.1~1%未満)抑うつ気分、(頻度不明)うつ病。
14). 腎及び尿路障害:(0.1~1%未満)夜間頻尿。
15). 生殖系及び乳房障害:(1%以上)不正子宮出血(33.5%)、乳房不快感、腟分泌物、乳房痛、外陰腟そう痒症、(0.1~1%未満)子宮頚管ポリープ、乳房圧痛、線維嚢胞性乳腺疾患、子宮ポリープ、子宮頚管分泌、性器分泌物、乳頭痛。
16). 呼吸器、胸郭及び縦隔障害:(0.1~1%未満)口腔咽頭痛、鼻乾燥。
17). 皮膚及び皮下組織障害:(0.1~1%未満)皮膚そう痒症、湿疹、アレルギー性皮膚炎、紅斑、ざ瘡、脂漏性皮膚炎、蕁麻疹、日光皮膚炎、発疹、(頻度不明)肝斑。
18). 免疫系障害:(頻度不明)アナフィラキシー反応。
19). 血管障害:(0.1~1%未満)高血圧。
- 授乳婦
- 治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること(母乳中に移行することがある)。
- 取扱い上の注意
- 14.1. 薬剤交付時の注意PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある)。
外箱開封後は遮光して保存すること。
- その他の注意
- 15.1. 臨床使用に基づく情報15.1.1. HRTと乳癌の危険性(1). 米国における閉経後女性を対象とした無作為化臨床試験(Women’s Health Initiative(WHI)試験)の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、乳癌になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.24)との報告がある。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、乳癌になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意差はない(ハザード比:0.80)との報告がある〔2.4、8.1、8.2参照〕。
(2). 英国における疫学調査(Million Women Study(MWS))の結果、卵胞ホルモン剤と黄体ホルモン剤を併用している女性では、乳癌になる危険性がHRT未実施群と比較して有意に高くなり(2.00倍)、この危険性は、併用期間が長期になるに従って高くなる(1年未満:1.45倍、1~4年:1.74倍、5~9年:2.17倍、10年以上:2.31倍)との報告がある〔2.4、8.1、8.2参照〕。
15.1.2. HRTと冠動脈性心疾患の危険性:米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、冠動脈性心疾患の危険性がプラセボ投与群と比較して高い傾向にあり、特に服用開始1年後では有意に高くなる(ハザード比:1.81)との報告がある。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、冠動脈性心疾患の危険性がプラセボ投与群と比較して有意差はない(ハザード比:0.91)との報告がある〔2.6参照〕。
15.1.3. HRTと脳卒中の危険性:米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、脳卒中(主として脳梗塞)の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.31)との報告がある。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、脳卒中(主として脳梗塞)の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.37)との報告がある〔2.6参照〕。
15.1.4. HRTと認知症の危険性:米国における65歳以上の閉経後女性を対象とした無作為化臨床試験(WHI Memory Study(WHIMS))の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群では、アルツハイマーを含む認知症の危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:2.05)との報告がある。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、アルツハイマーを含む認知症の危険性がプラセボ投与群と比較して有意ではないが、高い傾向がみられた(ハザード比:1.49)との報告がある。
15.1.5. HRTと卵巣癌の危険性(1). 米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群において、卵巣癌になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意ではないが、高い傾向がみられた(ハザード比:1.58)との報告がある〔2.5参照〕。
(2). 卵胞ホルモン剤を長期間使用した閉経期以降の女性では、卵巣癌になる危険性がHRT未実施群の女性と比較して高くなるとの疫学調査の結果が報告されている〔2.5参照〕。
15.1.6. HRTと胆のう疾患の危険性:米国におけるWHI試験の結果、結合型エストロゲン・黄体ホルモン配合剤投与群において、胆のう疾患になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.59)との報告がある。並行して行われた子宮摘出者に対する試験の結果、結合型エストロゲン単独投与群では、胆のう疾患になる危険性がプラセボ投与群と比較して有意に高くなる(ハザード比:1.67)との報告がある。
16.1 血中濃度
16.1.1 単回投与
健康閉経後成人女性12例に本剤200mgを絶食時に単回経口投与したときの薬物動態パラメータは次のとおりである。
単回投与時の薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
16.1.2 反復投与
健康閉経後成人女性計20例に本剤100mg又は200mgを絶食時に1日1回7日間反復経口投与した。Cmax及びAUCはいずれも100mg投与群と200mg投与群で用量依存性を示した。本剤100mg又は200mgを1日1回反復経口投与したときの薬物動態パラメータは次のとおりである。
反復投与時(1回100mg/日又は200mg/日)の薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
16.2 吸収
健康閉経後成人女性12例に、本剤200mgを絶食時及び食後に単回経口投与したとき、AUC及びCmaxは絶食時投与に比べ食後投与で上昇する傾向が示された。また、tmax及びt1/2は食事の影響を受けないことが示された。[7.参照]
絶食下及び食後の薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
16.3 分布
in vitro試験において、ヒト血清蛋白への結合率は約97%と報告されている。
16.4 代謝
主に肝臓において代謝される。代表的な代謝産物はプレグナノロン及びプレグナンジオールであり、これらはさらにグルクロン酸抱合体及び硫酸抱合体に代謝される。
16.5 排泄
14C‐標識プロゲステロンをヒトに静脈内投与した際、尿中に投与した放射能の約50%、胆汁中に約30%、糞中に約13%が排泄された(外国人データ)。
17.1 有効性及び安全性に関する試験
17.1.1 国内第III相試験
子宮を有する更年期障害又は卵巣欠落症状を有する女性349例に、エストラジオール0.5mg又は1.0mg経口投与の併用下で、本剤を1周期(28日)の1~28日目まで1日1回100mgを就寝前に経口投与(持続的投与法)、又は1周期(28日)の15~28日目まで1日1回200mgを就寝前に52週間経口投与(周期的投与法)した。
その結果、投与12週から52週において子宮内膜増殖症は認められなかった。
副作用発現頻度は54.2%(189/349例)であった。主な副作用は、不正子宮出血が33.5%(117/349例)、乳房不快感が4.6%(16/349例)、頭痛が3.2%(11/349例)、下腹部痛、浮動性めまいが2.9%(10/349例)、腹部膨満、便秘が2.3%(8/349例)、腟分泌物が2.0%(7/349例)であった。なお、不正子宮出血の投与法別の副作用発現頻度は持続的投与法で18.2%(31/170例)、周期的投与法で48.0%(86/179例)であった。また、重篤な副作用として乳管内増殖性病変0.3%(1/349例)、乳腺浸潤性小葉癌0.3%(1/349例)の発現が認められた。
18.1 作用機序
プロゲステロンは、子宮内膜上皮細胞に発現するプロゲステロン受容体に結合してエストロゲン受容体の遺伝子発現を抑制すること、及び子宮内膜間質細胞に発現するプロゲステロン受容体に結合して線維芽細胞増殖関連因子の産生を抑制することにより、エストロゲン受容体が制御する細胞増殖関連因子の産生を抑制し、卵胞ホルモンによる子宮内膜上皮細胞の増殖を抑制すると考えられる。
18.2 子宮内膜増殖抑制作用
卵巣摘出マウスにおいて、プロゲステロンは、5日間反復皮下投与することでエストロゲンによる子宮内膜上皮細胞の増殖を抑制した。ウサギにおいても、単回又は2日間反復筋肉内投与によって、エストロゲンによる子宮腺上皮細胞の増殖を抑制した。
卵巣摘出マウスにおいて、プロゲステロンは、3週間持続皮下投与することでエストロゲンによる子宮重量増加及び子宮内膜上皮細胞の増殖を抑制した。ウサギにおいて、40日間反復筋肉内投与することでエストロゲンによる子宮内膜増殖症の発症を抑制した。
- 一包可:不可
- 分割:不可
- 粉砕:不明
- 製造販売会社
- 富士製薬
- 販売会社
おくすりのQ&A
自費で接種された、風疹ワクチンが申請により
補助が受けれることになり、母子手帳記載以外に、予診票の控えがいるとのこと
保管中の予診票の控えを渡したら...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。