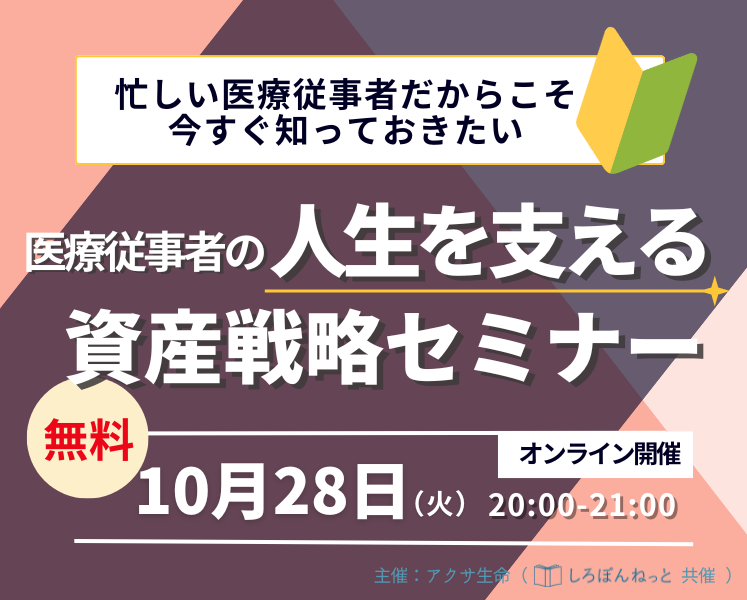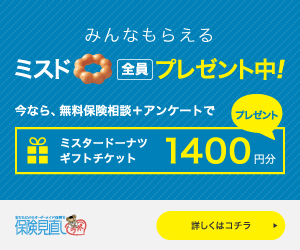アビガン錠200mg

添付文書情報2024年06月改定(第2版)
商品情報
- 習
- 処
- 生
- 特生
- 特承
- 毒
- 劇
- 麻
- 覚
- 覚原
- 向
- 警告
- 1.1. 〈重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症〉本剤は重症感染症診療体制が整備され、緊急時に十分な措置が可能な医療機関において、本剤について十分な知識をもつ医師のもと、入院管理下で投与すること。
1.2. 〈効能共通〉動物実験において、本剤は初期胚致死及び催奇形性が確認されていることから、妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと〔1.4、2.1、9.5妊婦の項参照〕。
1.3. 〈効能共通〉妊娠する可能性のある女性に投与する場合は、投与開始前に妊娠検査を行い、妊娠検査が陰性であることを確認した上で、投与を開始すること。また、その危険性について十分に説明した上で、投与期間中及び投与終了後10日間はパートナーと共に極めて有効な避妊法の実施を徹底するよう指導すること。なお、本剤の投与期間中に妊娠が疑われる場合には、直ちに投与を中止し、医師等に連絡するよう患者を指導すること〔9.4.1参照〕。
1.4. 〈効能共通〉治療開始に先立ち、患者又はその家族等に有効性及び危険性(胎児への曝露の危険性を含む)を十分に文書にて説明し、同意を得てから投与を開始すること〔1.2、2.1、9.5妊婦の項参照〕。
1.5. 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉本剤の投与にあたっては、本剤の必要性を慎重に検討すること。
- 禁忌
- 2.1. 妊婦又は妊娠している可能性のある女性〔1.2、1.4、9.5妊婦の項参照〕。
2.2. 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。
- 効能・効果
- 1). 新型インフルエンザウイルス感染症又は再興型インフルエンザウイルス感染症(ただし、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分なものに限る)。
2). 重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症。
(効能又は効果に関連する注意)
5.1. 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉本剤は、他の抗インフルエンザウイルス薬が無効又は効果不十分な新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症が発生し本剤を当該インフルエンザウイルスへの対策に使用すると国が判断した場合にのみ患者への投与が検討される医薬品である。本剤の使用に際しては、国が示す当該インフルエンザウイルスへの対策の情報を含め、最新の情報を随時参照し、適切な患者に対して使用すること。
5.2. 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉本剤は細菌感染症には効果がない〔8.3参照〕。
5.3. 〈効能共通〉小児等に対する投与経験はない〔9.7小児等の項参照〕。
- 用法・用量
- 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉
通常、成人にはファビピラビルとして1日目は1回1600mgを1日2回、2日目から5日目は1回600mgを1日2回経口投与する。総投与期間は5日間とすること。
〈重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症〉
通常、成人にはファビピラビルとして1日目は1回1800mgを1日2回、2日目から10日目は1回800mgを1日2回経口投与する。総投与期間は10日間とすること。
(用法及び用量に関連する注意)
7.1. 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉インフルエンザ様症状の発現後速やかに投与を開始すること。
7.2. 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉承認用法及び用量における本剤の有効性及び安全性が検討された臨床試験は実施されていない。承認用法及び用量は、インフルエンザウイルス感染症患者を対象としたプラセボ対照第1/2相試験成績及び国内外薬物動態データに基づき推定した〔16.1.1、17.1.1参照〕。
7.3. 〈重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症〉重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症の症状の発現後速やかに投与を開始すること。
- 生殖能を有する者
- 8.1. 〈効能共通〉肝機能障害があらわれることがあるので、投与開始前及び投与中は肝機能検査を実施し、観察を十分に行うこと〔9.3.1、9.3.2、11.1.4参照〕。
8.2. 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無又は種類にかかわらず、インフルエンザ罹患時には、異常行動を発現した例が報告されている。
異常行動による転落等の万が一の事故を防止するための予防的な対応として、新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症の場合①異常行動発現のおそれがあること、②自宅において療養を行う場合少なくとも発熱から2日間、保護者等は転落等の事故に対する防止対策を講じることについて患者・家族に対し説明を行うこと。
なお、新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症の場合、転落等の事故に至るおそれのある重度の異常行動については、就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多いこと、発熱から2日間以内に発現することが多いこと、が知られている〔11.1.1参照〕。
8.3. 〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉細菌感染症がインフルエンザウイルス感染症に合併したり、インフルエンザ様症状と混同されることがあるので、新型インフルエンザウイルス感染症で細菌感染症又は再興型インフルエンザウイルス感染症で細菌感染症の場合及び細菌感染症が疑われる場合には、抗菌剤を投与するなど適切な処置を行うこと〔5.2参照〕。
9.1.1. 痛風又は痛風の既往歴のある患者及び高尿酸血症のある患者:血中尿酸値が上昇し、痛風発作があらわれることがある〔11.2参照〕。
9.3.1. 重度肝機能障害患者(Child-Pugh分類クラスC):投与は推奨されない(本剤投与の可否はリスクとベネフィットを考慮して慎重に判断すること(本剤の曝露量が著しく増加し、副作用が強くあらわれるおそれがある))〔8.1、16.6.1参照〕。
9.3.2. 軽度及び中等度肝機能障害患者(Child-Pugh分類クラスA及びB):投与開始前にリスクを十分に検討し、慎重に投与すること(本剤の曝露量が増加し、副作用が強くあらわれるおそれがある)〔8.1、16.6.1参照〕。
9.4.1. 妊娠する可能性のある女性:投与開始前に妊娠検査を行い、妊娠検査が陰性であることを確認した上で、投与を開始し、また、妊娠する可能性のある女性には、その危険性について十分に説明した上で、投与期間中及び投与終了後10日間はパートナーと共に極めて有効な避妊法の実施を徹底するよう指導すること。なお、本剤の投与期間中に妊娠が疑われる場合には、直ちに投与を中止し、医師等に連絡するよう患者を指導すること〔1.3、9.5妊婦の項参照〕。
- 相互作用
- 本剤は主にアルデヒドオキシダーゼ(AO)、一部はキサンチンオキシダーゼ(XO)により代謝される。また、AO及びチトクロームP-450(CYP)2C8を阻害する〔16.4、16.7.1参照〕。
10.2. 併用注意:1). ピラジナミド[血中尿酸値が上昇する;ピラジナミド1.5g1日1回、本剤1200mg/400mg1日2回が投与されたとき、血中尿酸値はピラジナミド単独及び本剤併用時で11.6・13.9mg/dLであった(腎尿細管における尿酸の再吸収を相加的に促進させる)]。
2). CYP2C8で代謝される薬剤(レパグリニド等)〔16.7.2参照〕[併用
薬剤の血中濃度が上昇し併用薬剤の副作用が発現するおそれがある(CYP2C8を阻害することにより、併用薬剤の血中濃度を上昇させる)]。
3). テオフィリン〔16.7.2参照〕[本剤の血中濃度が上昇し本剤の副作用が発現するおそれがある(XOを介した相互作用により、本剤の血中濃度を上昇させることが考えられる)]。
4). ファムシクロビル、スリンダク[これらの薬剤の効果を減弱させるおそれがある(本剤がAOを阻害することにより、これらの薬剤の活性化体の血中濃度を低下させることが考えられる)]。
- 副作用
- 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 重大な副作用
- 11.1. 重大な副作用
11.1.1. 異常行動(頻度不明):因果関係は不明であるものの、インフルエンザ罹患時には、転落等に至るおそれのある異常行動(急に走り出す、徘徊する等)があらわれることがある〔8.2参照〕。
11.1.2. ショック、アナフィラキシー(いずれも頻度不明)。
11.1.3. 肺炎(頻度不明)。
11.1.4. 劇症肝炎(頻度不明)、肝機能障害(0.2%)、黄疸(頻度不明)〔8.1参照〕。
11.1.5. 中毒性表皮壊死融解症(Toxic Epidermal Necrolysis:TEN)、皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(いずれも頻度不明)。
11.1.6. 急性腎障害(頻度不明)。
11.1.7. 白血球減少、好中球減少、血小板減少(いずれも頻度不明)。
11.1.8. 痙攣(0.2%)、精神神経症状(意識障害、譫妄、幻覚、妄想等)(頻度不明)。
11.1.9. 出血性大腸炎(頻度不明)。
- 11.2. その他の副作用
1). 過敏症:(1%以上)発疹、(0.5%未満)湿疹、そう痒症、紅斑。
2). 肝臓:(1%以上)AST増加、ALT増加、γ-GTP増加、(0.5%未満)血中ALP増加、血中ビリルビン増加。
3). 腎臓:(0.5~1%未満)尿中ブドウ糖陽性、(0.5%未満)尿中血陽性。
4). 消化器:(1%以上)下痢(4.5%)、(0.5~1%未満)悪心、腹痛、嘔吐、(0.5%未満)腹部不快感、胃炎、十二指腸潰瘍、血便排泄、口内炎。
5). 血液:(1%以上)好中球数減少、白血球数減少、(0.5%未満)白血球数増加、網状赤血球数減少、単球数増加、リンパ節症。
6). 代謝異常:(1%以上)*血中尿酸増加(7.0%)、血中トリグリセリド増加、(0.5%未満)*痛風、血中カリウム減少。
7). 呼吸器:(0.5%未満)喘息、口腔咽頭痛、鼻炎、鼻咽頭炎、誤嚥性肺炎。
8). その他:(0.5%未満)味覚異常、血中CK増加、心電図QT延長、扁桃腺ポリープ、蜂巣炎、霧視、眼痛、回転性めまい、上室性期外収縮、心室性期外収縮、心電図ST-T部分異常、心電図T波逆転、色素沈着、筋肉痛、挫傷、(頻度不明)発熱。
*)〔9.1.1参照〕。
- 高齢者
- 患者の状態を観察しながら投与すること。一般に生理機能が低下していることが多い。
- 授乳婦
- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないこと(動物実験において、臨床曝露量と同程度又は下回る用量で初期胚致死(ラット)及び催奇形性(サル、マウス、ラット及びウサギ)が認められている)〔1.2、1.4、2.1、9.4.1参照〕。
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること(本剤の主代謝物である水酸化体がヒト母乳中へ移行することが認められている)。
- 小児等
- 小児等を対象とした臨床試験は実施していない(動物実験において、幼若イヌ[8週齢]に1ヵ月間投与した試験では、若齢イヌ[7~8ヵ月齢]の致死量より低用量(60mg/kg/日)で投与20日以降に途中死亡例が認められており、幼若動物(ラット[6日齢]及びイヌ[8週齢])では、異常歩行、骨格筋線維萎縮及び骨格筋線維空胞化、心乳頭筋変性/心乳頭筋壊死及び心乳頭筋鉱質沈着などが認められている)〔5.3参照〕。
- 適用上の注意
- 14.1. 薬剤交付時の注意PTP包装の薬剤はPTPシートから取り出して服用するよう指導すること(PTPシートの誤飲により、硬い鋭角部が食道粘膜へ刺入し、更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することがある)。
- その他の注意
- 15.2. 非臨床試験に基づく情報動物実験において、ラット[12週齢]及び若齢イヌ[7~8ヵ月齢]で精巣病理組織学的変化、マウス[11週齢]で精子異常が認められている(なお、いずれも休薬により回復又は回復傾向が認められている)。
16.1 血中濃度
16.1.1 反復投与(1600mg/600mg BID)
健康成人8例に本剤を1日目は1回1600mgを1日2回、2日目から6日目は1回600mgを1日2回(6日目は1回のみ)経口投与(1600mg/600mg BID)したときの薬物動態パラメータは次のとおりであった。[7.2参照]
本剤の薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
図1 本剤の血漿中濃度推移(平均値±標準偏差)
16.1.2 反復投与(1800mg/800mg BID)
健康成人8例に本剤を1日目は1回1800mgを1日2回、2日目から22日目は1回800mgを1日2回(22日目は1回のみ)経口投与(1800mg/800mg BID)したときの薬物動態パラメータは次のとおりであった。
本剤の薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
図2 本剤の血漿中濃度推移(平均値±標準偏差)
16.1.3 アルデヒドオキシダーゼ活性が低いと考えられる者
アルデヒドオキシダーゼ(AO)活性がほとんどないと考えられる健康成人1例に本剤を7日間反復経口投与[本剤を1日目初回は1200mg、1日目2回目は400mg、2日目から6日目は1回400mgを1日2回、7日目は400mgを1回投与]注10)したとき、投与1日目及び投与7日目の未変化体のAUCの推定値は、それぞれ1452.73μg・hr/mL及び1324.09μg・hr/mLであった。
16.2 吸収
16.2.1 食事の影響
健康成人15例にクロスオーバー法により本剤1200mgを空腹時及び食後に単回経口投与注10)したところ、本剤の空腹時に対する食後投与のCmax及びAUCの幾何平均の比[90%信頼区間]は、それぞれ0.908[0.826、0.998]及び0.963[0.888、1.044]であり、比の90%信頼区間はあらかじめ定めた範囲内(0.80~1.25)であった。
16.3 分布
16.3.1 精液への分布
健康成人男性20例に本剤を1日目は1回1200mgを1日2回、2日目から5日目は1回800mgを1日2回経口投与(1200mg/800mg BID)注10)したときの本剤の精液中濃度(幾何平均)は投与3日目及び投与終了後2日目でそれぞれ18.341μg/mL及び0.053μg/mLであり、投与終了後7日目にはすべての被験者で定量下限(0.02μg/mL)未満となった。また、精液/血漿中濃度比(平均値)は投与3日目及び投与終了後2日目でそれぞれ0.53及び0.45であった(外国人データ)。
16.3.2 血清蛋白結合率
本剤のヒト血清蛋白結合率は、0.3~30μg/mLの濃度において、53.4~54.4%であった(in vitro、遠心限外濾過法)。
16.3.3 動物でのデータ
サルに14C‐ファビピラビルを単回経口投与したとき、各組織に広く移行した。各組織の放射能濃度は投与後0.5時間に最高値を示した後、血漿中放射能濃度と平行した推移を示した。投与後0.5時間の肺内放射能濃度の血漿中濃度比は0.51であり、投与後、呼吸器系組織に速やかに移行した。また、投与後0.5時間の腎臓中放射能濃度は血漿中よりも高く、血漿中濃度比は2.66であった。骨を除く各組織の放射能濃度は、投与後24時間までに最高濃度の2.8%次に低下した。
16.4 代謝
本剤はチトクロームP‐450(CYP)で代謝されず、主にAO、一部はキサンチンオキシダーゼ(XO)により水酸化体に代謝された。ヒト肝サイトゾルを用いて本剤の代謝を検討した結果、水酸化体の生成は3.98~47.6pmol/mg protein/minであり、AO活性には最大で12倍の個体間差が認められた。また、水酸化体以外の代謝物として、ヒト血漿中及び尿中にグルクロン酸抱合体が認められた。[10.参照]
16.5 排泄
本剤は主に水酸化体として尿中に排泄され、未変化体はわずかであった。健康成人6例に本剤を7日間反復経口投与[本剤を1日目初回は1200mg、1日目2回目は400mg、2日目から6日目は1回400mgを1日2回、7日目は400mgを1回投与]注10)したときの最終投与後48時間までの未変化体及び水酸化体の累積尿中排泄率は、それぞれ0.8%及び53.1%であった。
16.6 特定の背景を有する患者
16.6.1 肝機能障害患者
軽度及び中等度肝機能障害患者(Child‐Pugh分類クラスA及びB、各6例)に、本剤を1日目は1回1200mgを1日2回、2日目から5日目は1回800mgを1日2回経口投与(1200mg/800mg BID)注10)したとき、投与5日目のCmax及びAUCは、健康成人に同様の用法及び用量で投与した場合と比べて、軽度肝機能障害患者ではそれぞれ約1.6倍及び約1.7倍、中等度肝機能障害患者ではそれぞれ約1.4倍及び約1.8倍であった。
重度肝機能障害患者(Child‐Pugh分類クラスC、4例)に、本剤を1日目は1回800mgを1日2回、2日目から3日目は1回400mgを1日2回経口投与(800mg/400mg BID)注10)したとき、投与3日目のCmax及びAUCは、健康成人に同様の用法及び用量で投与した場合と比べて、それぞれ約2.1倍及び約6.3倍であった(外国人データ)。[9.3.1、9.3.2参照]
16.6.2 腎機能障害患者
軽度、中等度及び重度腎機能障害患者(CLcr:60~89mL/min、30~59mL/min及び30mL/min未満の透析していない患者、各4例)に、本剤1800mgを単回経口投与注10)したとき、Cmax及びAUCinfは、本剤1800mgを単回経口投与した健康成人と比べて、軽度腎機能障害患者ではそれぞれ約1.0倍及び約1.2倍、中等度腎機能障害患者ではいずれも約0.9倍、重度腎機能障害患者ではそれぞれ約1.0倍及び約1.2倍であった。
本剤の代謝物である水酸化体のCmax及びAUCinfは、本剤1800mgを単回経口投与した健康成人と比べて、軽度腎機能障害患者ではそれぞれ約1.1倍及び約1.2倍、中等度腎機能障害患者ではそれぞれ約1.6倍及び約2.2倍、重度腎機能障害患者ではそれぞれ約2.5倍及び約6.5倍であった(外国人データ)。
注10)本剤の承認用法及び用量は、「1日目は1回1600mgを1日2回、2日目から5日目は1回600mgを1日2回経口投与」又は「1日目は1回1800mgを1日2回、2日目から10日目は1回800mgを1日2回経口投与」
16.7 薬物相互作用
16.7.1 非臨床薬物相互作用試験
本剤はAO活性を不可逆的に阻害した。また、CYP2C8、CYP3A、OAT1、OAT3、MATE1及びMATE2‐Kを阻害した。[10.参照]
16.7.2 臨床薬物相互作用試験
臨床薬物相互作用試験の結果は次のとおりであった。[10.2参照]
本剤の薬物動態に及ぼす併用薬剤の影響
→図表を見る(PDF)
併用薬剤の薬物動態に及ぼす本剤の影響
→図表を見る(PDF)
17.1 有効性及び安全性に関する試験
〈新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症〉
17.1.1 海外第I/II相試験
A型又はB型インフルエンザウイルス感染症患者(成人)を対象として、プラセボを対照とした第I/II相試験[本剤を1日目は1回1800mgを1日2回、2日目から5日目は1回800mgを1日2回経口投与(1800mg/800mg BID)及び本剤を1日目初回は2400mg、2回目及び3回目は1回600mg、2日目から5日目は1回600mgを1日3回経口投与(2400mg/600mg TID)]注1)を実施した。主要評価項目である罹病期間注2)について、プラセボ群(88例)と本剤1800mg/800mg BID群(101例)との対比較では、統計学的に有意な差が認められたが(p=0.01、Gehan‐Wilcoxon test)、本剤2400mg/600mg TID群(82例)との対比較では、統計学的に有意な差は認められなかった(p=0.414、Gehan‐Wilcoxon test)。本剤群において、副作用は認められなかった。[7.2参照]
図1 インフルエンザ主要症状罹病期間
17.1.2 海外第III相試験
A型又はB型インフルエンザウイルス感染症患者(成人)を対象として、プラセボを対照とした第III相試験[本剤を1日目は1800mgを1日2回、2日目から5日目は1回800mgを1日2回経口投与(1800mg/800mg BID)]注1)について、主要評価項目をインフルエンザ主要症状罹病期間注3)と設定し、実施した結果は次のとおりであった。
主要解析結果(ITTI集団)
→図表を見る(PDF)
図2 主要評価項目注3)に係るKaplan‐Meierプロット図(ITTI集団)
注3)インフルエンザ主要6症状(咳嗽、咽頭痛、頭痛、鼻閉、筋肉痛、全身倦怠感)及び発熱が「改善」するまでの時間。インフルエンザ主要6症状のすべてが消失あるいは軽度となり、かつ発熱が回復した状態を21.5時間持続した場合を「改善」と定義。
副作用発現頻度は、本剤群で7.9%(34/428例)で、主な副作用は、浮動性めまい1.2%(5/428例)であった。
17.1.3 海外第III相試験
A型又はB型インフルエンザウイルス感染症患者(成人)を対象として、プラセボを対照とした第III相試験[本剤を1日目は1800mgを1日2回、2日目から5日目は1回800mgを1日2回経口投与(1800mg/800mg BID)]注1)について、主要評価項目をインフルエンザ主要症状罹病期間注3)と設定し、実施した結果は次のとおりであった。
主要解析結果(ITTI集団)
→図表を見る(PDF)
図3 主要評価項目注3)に係るKaplan‐Meierプロット図(ITTI集団)
注3)インフルエンザ主要6症状(咳嗽、咽頭痛、頭痛、鼻閉、筋肉痛、全身倦怠感)及び発熱が「改善」するまでの時間。インフルエンザ主要6症状のすべてが消失あるいは軽度となり、かつ発熱が回復した状態を21.5時間持続した場合を「改善」と定義。
副作用発現頻度は、本剤群で10.2%(88/861例)で、主な副作用は、血中トリグリセリド増加2.0%(17/861例)、悪心1.5%(13/861例)、下痢1.3%(11/861例)であった。
17.1.4 国際共同第III相試験(参考)
A型又はB型インフルエンザウイルス感染症患者(成人)を対象として、オセルタミビルリン酸塩(1回75mg1日2回、5日間)を対照とした国際共同第III相試験[本剤を1日目初回は1200mg、1日目2回目は400mg、2日目から5日目は1回400mgを1日2回経口投与]注1)を実施した[757例(日本540例、韓国78例、台湾139例)]。インフルエンザ主要症状罹病期間注4)の中央値[95%信頼区間]は、本剤群(377例)で63.1[55.5、70.4]時間、オセルタミビルリン酸塩群(380例)で51.2[45.9、57.6]時間であり、オセルタミビルリン酸塩群に対する本剤群のハザード比[95%信頼区間]は、0.818[0.707、0.948]であり、本剤の有効性は示されなかった(p=0.007、log‐rank test)。
副作用発現頻度は、本剤群で19.8%(75/378例)であった。主な副作用は、血中尿酸増加5.6%(21/378例)、下痢4.2%(16/378例)、血中トリグリセリド増加1.9%(7/378例)であった。
17.1.5 海外第II相試験(参考)
A型又はB型インフルエンザウイルス感染症患者(成人)を対象として、プラセボを対照とした海外第II相試験[本剤を1日目は1回1000mgを1日2回、2日目から5日目は1回400mgを1日2回経口投与(1000mg/400mg BID)、本剤を1日目は1回1200mgを1日2回、2日目から5日目は1回800mgを1日2回経口投与(1200mg/800mg BID)及びプラセボを1日2回経口投与]注1)を実施した。インフルエンザ主要症状罹病期間注5)の中央値[95%信頼区間]は、本剤1000mg/400mg BID群(88例)で100.4[82.4、119.8]時間、本剤1200mg/800mg BID群(121例)で86.5[79.2、102.1]時間、プラセボ群(124例)で91.9[70.3、105.4]時間であり、プラセボ群との対比較において、本剤群のいずれにおいても、統計学的に有意な差は認められなかった(p>0.05、Gehan‐Wilcoxon test、検定の多重性はStep‐down法で調整)。
副作用発現頻度は、本剤1000mg/400mg BID群で18.9%(25/132例)、本剤1200mg/800mg BID群で19.6%(37/189例)であった。主な副作用は、本剤1000mg/400mg BID群で下痢2.3%(3/132例)、血中尿酸増加2.3%(3/132例)、本剤1200mg/800mg BID群で下痢3.2%(6/189例)、血中尿酸増加3.2%(6/189例)であった。
注1)本剤の新型又は再興型インフルエンザウイルス感染症に対する承認用法及び用量は、「1日目は1回1600mgを1日2回、2日目から5日目は1回600mgを1日2回経口投与」
注2)インフルエンザ主要6症状(咳嗽、咽頭痛、頭痛、鼻閉、筋肉痛、全身倦怠感)及び発熱の持続時間
注3)インフルエンザ主要6症状(咳嗽、咽頭痛、頭痛、鼻閉、筋肉痛、全身倦怠感)及び発熱が「改善」するまでの時間。インフルエンザ主要6症状のすべてが消失あるいは軽度となり、かつ発熱が回復した状態を21.5時間持続した場合を「改善」と定義。
注4)治験薬投与開始後から7つのインフルエンザ主要症状[咳嗽、咽喉頭痛、頭痛、鼻閉、熱感、筋肉痛及び全身倦怠感]がすべて「改善」するまでの時間(すべてのスコアが「1」以下に達した時点)。患者日誌をもとに治験責任医師又は治験分担医師がスコア化したインフルエンザ症状が「1」以下となってから21.5時間以上そのスコアを維持した状態を「改善」と定義。
注5)インフルエンザ主要6症状(咳嗽、咽頭痛、頭痛、鼻閉、筋肉痛、全身倦怠感)がすべて「改善」するまでの時間(すべてのスコアが「1」以下に低下した時点)及び発熱が20歳以上65歳未満の患者では38℃以下、65歳以上の患者では37.8℃以下を21.5時間以上維持した状態。
〈重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症〉
17.1.6 国内第III相試験
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)患者を対象として、国内第III相試験[本剤を1日目は1回1800mgを1日2回、2日目から10日目は1回800mgを1日2回経口投与]を実施した。主たる有効性解析対象例(mITTE)注6)における、主要評価項目である本剤投与開始から28日目までの累積致死率は15.8%(3/19例)[95%信頼区間:3.4、39.6%]であり、事前設定された致死率の閾値(12.5%)注7)の点推定値を上回った。
副作用発現頻度は70.0%(21/30例)で、主な副作用は、高尿酸血症23.3%(7/30例)、血中尿酸増加20.0%(6/30例)、高トリグリセリド血症10.0%(3/30例)、発疹6.7%(2/30例)、心電図QT延長6.7%(2/30例)であった。
注6)国立感染症研究所で実施したRT‐PCR検査でSFTSウイルスが検出され、症状発症後5日以内(144時間以内)に本剤を投与開始した症例(modified intention‐to‐treat evaluable)
注7)2015年1月から2017年9月における国立感染症研究所の感染症発生動向調査の累積致死率(2016年に実施した医師主導臨床研究で本剤を投与した10例を除く)
18.1 作用機序
細胞内でリボシル三リン酸体(ファビピラビルRTP)に代謝され、ファビピラビルRTPがインフルエンザウイルスや重症熱性血小板減少症候群(SFTS)ウイルスの複製に関与するRNAポリメラーゼを選択的に阻害すると考えられている。ヒト由来DNAポリメラーゼα、β及びγに対して、ファビピラビルRTP(1000μmol/L)は、αへの阻害作用は示さず、βに対して9.1~13.5%、γに対して11.7~41.2%の阻害作用を示した。また、ファビピラビルRTPのヒト由来RNAポリメラーゼIIに対する阻害作用(IC50値)は、905μmol/Lであった。
18.2 In vitro抗ウイルス活性
A型及びB型インフルエンザウイルス実験室株に対するEC50値は、0.014~0.55μg/mLであり、抗ウイルス活性を示した。
アダマンタン(アマンタジン及びリマンタジン)、オセルタミビル及びザナミビル耐性株を含む季節性のA型及びB型インフルエンザウイルスに対するEC50値は、それぞれ0.03~0.94μg/mL及び0.09~0.83μg/mLであった。
豚由来A型及び高病原性株を含む鳥由来A型(H5N1、H7N9株を含む)をはじめとするA型インフルエンザウイルス(アダマンタン、オセルタミビル及びザナミビル耐性株を含む)に対するEC50値は、0.06~3.53μg/mLであった。
アダマンタン、オセルタミビル及びザナミビル全てに耐性のA型及びB型インフルエンザウイルスに対するEC50値は0.09~0.47μg/mLであり、交差耐性を示さなかった。
SFTSウイルスの各種臨床分離株(J1型、J2型、J3型、C3型、C4型及びC5型)に対して抗ウイルス活性を示し、EC90値は14.83~38.73μmol/L(2.33~6.08μg/mL)、EC99値は48.20~79.40μmol/L(7.57~12.47μg/mL)であった。
18.3 動物モデルにおける治療効果
インフルエンザウイルスA(H7N9)、A(H1N1)pdm09及びA(H3N2)によるマウス感染モデルにおいて、60mg/kg/日以下の5日間経口投与により肺内ウイルス量を低下させた。
インフルエンザウイルスA(H3N2)及びA(H5N1)によるマウス感染モデルにおいて、30mg/kg/日の5日間経口投与により治療効果を示した。
また、インフルエンザウイルスA(H3N2)による重症複合型免疫不全マウス感染モデルにおいて、30mg/kg/日の14日間の経口投与により治療効果を示した。
SFTSウイルスによるマウス感染モデルにおいて、120mg/kg/日及び200mg/kg/日の5日間経口投与により、生存率及び体重変化を指標とする治療効果を示し、血中ウイルスRNA量を低下させた。
18.4 耐性
ファビピラビル存在下で30代まで継代したA型インフルエンザウイルスのファビピラビルに対する感受性に変化はなく、耐性ウイルスは選択されなかった。なお、国際共同第III相試験をはじめとする臨床試験において、本剤耐性インフルエンザウイルスの出現状況に関する情報は得られていない。
ファビピラビル存在下で10代まで継代したSFTSウイルスにおいて、ファビピラビルに対する感受性の低下は観察されず、耐性ウイルスは選択されなかった。なお、国内第III相試験において、本剤耐性SFTSウイルスの出現状況に関する情報は得られていない。
- 一包可:不可
- 分割:不可
- 粉砕:不明
- 製造販売会社
- 富士フイルム富山化学
- 販売会社
おくすりのQ&A
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。