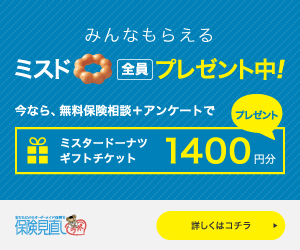アナエブリ皮下注200mgペン

添付文書情報2025年04月改定(第1版)
商品情報
- 禁忌
- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者。
- 効能・効果
- 遺伝性血管性浮腫の急性発作の発症抑制。
(効能又は効果に関連する注意)
臨床試験において、侵襲を伴う処置による急性発作の発症抑制に対する有効性及び安全性は検討されていない。
- 用法・用量
- 通常、成人及び12歳以上の小児には、ガラダシマブ(遺伝子組換え)として初回に400mgを皮下投与し、以降は200mgを月1回皮下投与する。
- 特定の背景を有する患者に関する注意
- 急性発作の治療を目的に本剤を使用しないことを患者又はその家族に十分に説明し、理解を得た上で使用すること。
- 副作用
- 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。
- 重大な副作用
- 11.1. 重大な副作用
11.1.1. 重篤な過敏症(頻度不明):アナフィラキシー等の重篤な過敏症があらわれることがある。
- 11.2. その他の副作用
一般・全身障害及び投与部位の状態:(5%以上)注射部位反応(注射部位内出血、注射部位紅斑、注射部位そう痒感)。
- 授乳婦
- 妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること(本剤はウサギにおいて胎盤通過が認められており、ヒトにおける胎盤通過性は不明であるが、本剤はヒトIgG4モノクローナル抗体であり、ヒトIgGは胎盤関門を通過することが知られている)。
治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること(本剤のヒト乳汁への移行は不明であるが、本剤はヒトIgG4モノクローナル抗体であり、ヒトIgGは乳汁中に移行することが知られている)。
- 小児等
- 12歳未満の小児等を対象とした有効性及び安全性を指標とした臨床試験は実施していない。
- 取扱い上の注意
- 14.1. 薬剤投与前の注意14.1.1. 投与前に冷蔵庫から取り出し、室温に戻しておくこと。
14.1.2. 投与前に内容物を目視により確認すること(異物や変色が認められる場合は使用しないこと)。
14.2. 薬剤投与時の注意14.2.1. 注射部位は腹部、大腿部又は上腕部とし、投与毎に注射部位を変えること。
14.2.2. 皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位<傷・発疹・発赤・硬結等>には注射しないこと。
14.2.3. 本剤は1回で全量を使用する製剤であり、再使用しないこと。
20.1. 外箱開封後は遮光して保存すること。
20.2. 凍結を避けて、冷蔵庫(2~8℃)で保存すること(冷蔵庫から出した後は25℃以下で保存し、使用期限を超えない範囲で2ヵ月以内に使用すること(冷蔵庫の外で保存した場合は、再び冷蔵庫に戻さないこと))。
- その他の注意
- 15.1. 臨床使用に基づく情報15.1.1. 遺伝性血管性浮腫患者を対象とした第2相試験及び第3相試験において、本剤の投与を受けた172例中5例(2.9%)に抗薬物抗体発現が認められた。抗薬物抗体の発現が認められた患者は少なく、抗薬物抗体の発現による本剤の薬物動態、有効性及び安全性への影響は明らかではない。
15.1.2. 遺伝性血管性浮腫患者を対象とした第2相試験及び第3相試験において、本剤200mg投与後166例中11例(6.6%)で基準値上限の1.5倍を上回る活性化部分トロンボプラスチン時間延長(基準値上限の1.5倍を上回るaPTT延長)が認められ、aPTT延長がみられた11例のうち、出血に関連する事象は1例(挫傷)認められたが、当該事象とaPTT延長の発現時期は異なっていた(また、11例のうち、基準値上限の2倍を上回るプロトロンビン時間延長は3例に認められた)。
16.1 血中濃度
16.1.1 単回投与
日本人健康成人(12例)に本剤200mgを単回皮下投与したときの薬物動態パラメータは次のとおりであった。
日本人健康成人(12例)における本剤200mg単回皮下投与時のガラダシマブの薬物動態パラメータ
→図表を見る(PDF)
16.1.2 反復投与
国際共同第III相試験において、遺伝性血管性浮腫1型又は2型(C1‐INH HAE)患者39例(日本人患者4例を含む)に本剤の初回用量400mgを皮下投与し、以降200mgを月1回皮下投与したときの本剤の血漿中トラフ濃度は次のとおりであった。定常状態における本剤の血漿中トラフ濃度は概ね一定であった。
C1‐INH HAE患者における本剤反復皮下投与時のガラダシマブの血漿中トラフ濃度
→図表を見る(PDF)
16.1.3 母集団薬物動態解析
母集団薬物動態解析において、本剤の初回用量400mgを皮下投与後、以降200mgを月1回皮下投与したHAE患者の薬物動態パラメータを検討した。定常状態における1投与間隔の血漿中濃度-時間曲線下面積(AUCtau,ss)、定常状態における最高血漿中濃度(Cmax,ss)及び定常状態における最低血漿中濃度(Cmin,ss)の平均値(標準偏差)は、それぞれ9,920(4,470)μg・h/mL、20.5(9.66)μg/mL及び8.94(4.64)μg/mLと推定された。初回用量400mgの皮下投与後に本剤の曝露は定常状態に達した。
HAE患者における本剤皮下投与後の血漿中最高濃度到達時間は約6日であった。
HAE患者における本剤の見かけの分布容積の平均値(標準偏差)は、8.36(5.55)Lであった。
HAE患者における本剤の見かけの全身クリアランスの平均値(標準偏差)は0.0243(0.0122)L/hであり、終末相の消失半減期は約18日であった。
健康成人及びHAE患者を対象とした母集団薬物動態解析における絶対的アベイラビリティは、0.387(95%信頼区間:0.344、0.431)と推定された。
16.2 吸収
健康成人において、注射部位(腹部、大腿部、上腕部)は本剤の曝露に影響しなかった(外国人データ)。
17.1 有効性及び安全性に関する試験
17.1.1 国際共同第III相試験
成人及び12歳以上の小児の遺伝性血管性浮腫1型又は2型(C1‐INH HAE)患者64例(日本人患者6例を含む)を対象とした、多施設共同プラセボ対照ランダム化二重盲検並行群間比較試験(本剤群39例、プラセボ群25例)を実施した。本試験は観察期(最長2ヵ月)及び治療期(6ヵ月)で構成され、投与期間は6ヵ月であった。本剤の初回用量400mgを最初の月に皮下投与し、以降200mgを月1回皮下投与した。主要評価項目である治療期6ヵ月間における治験責任医師が確認した月間HAE発作回数注1)は次表のとおりであった。本剤群とプラセボ群との対比較で統計的に有意な差が認められた。
注1)治療期(Day1[本剤の初回投与日]からDay182までの期間)の期間で調整した月当たりのHAE発作回数
治療期6ヵ月における治験責任医師が確認した月間HAE発作回数(有効性解析対象集団)
→図表を見る(PDF)
治療期6ヵ月間における副作用は、本剤群で39例中4例(10.3%)、プラセボ群で25例中3例(12.0%)に発現した。主な副作用は注射部位反応であり、本剤群で2例(5.1%)に注射部位紅斑、注射部位内出血及び注射部位そう痒感が各1件認められ、プラセボ群で2例(8.0%)に注射部位紅斑が2件認められた。
18.1 作用機序
本剤は活性型血液凝固第XII因子(FXIIa)の触媒ドメインに結合し、その触媒活性を阻害する。第XII因子は接触活性化経路で最初に活性化される因子であり、炎症性ブラジキニン産生カリクレイン‐キニン系を開始する。本剤はプレカリクレインからカリクレインへの活性化を抑制し、それに続く遺伝性血管性浮腫の発作における炎症及び腫脹に関連するブラジキニンの生成を抑制する。
18.2 薬理作用
18.2.1 In vitro薬理試験において、62.5nMのヒトFXIIa存在下におけるガラダシマブのFXIIa活性阻害に対するIC50は15nMであった。
18.2.2 In vitro薬理試験において、デキストラン硫酸による接触相活性化後のヒト血漿中のブラジキニン産生を阻害した。
18.2.3 In vivoマウス受動的アナフィラキシーモデルにおいて、ガラダシマブは血管透過性の亢進を抑制した。
- 製造販売会社
- CSLベーリング
- 販売会社
おくすりのQ&A
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。