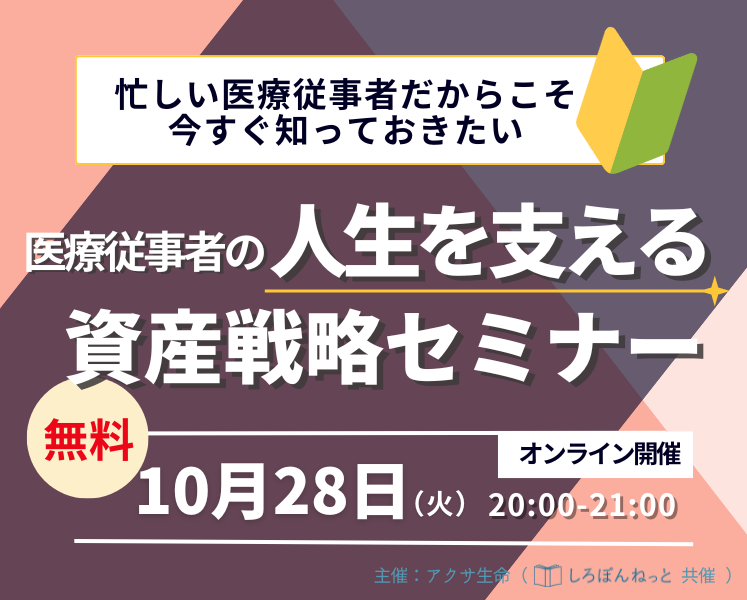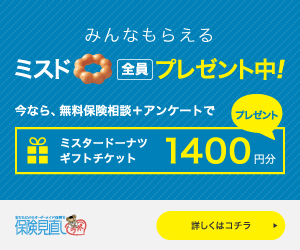令和6年 第10部 麻酔
通則
1 麻酔の費用は、第1節及び第2節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。ただし、麻酔に当たって別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、第1節及び第2節の各区分の所定点数に第3節の所定点数を合算した点数により算定する。
2 6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対して麻酔を行った場合は、全身麻酔の場合を除き、当該麻酔の所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。
3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
4 入院中の患者以外の患者に対し、緊急のために、休日に処置及び手術を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置及び手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80又は100分の40若しくは100分の80に相当する点数を加算した点数により算定し、入院中の患者に対し、緊急のために、休日に処置若しくは手術を行った場合又はその開始時間が深夜である処置若しくは手術を行った場合の麻酔料は、それぞれ所定点数の100分の80に相当する点数を加算した点数により算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、入院中の患者以外の患者に対し、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置及び手術を行った場合は、所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
5 第10部に掲げる麻酔料以外の麻酔料の算定は、医科点数表の例による。
通知
通則
1 「通則2」から「通則4」までの規定は、第1節の所定点数(酸素及び窒素を使用した場合の加算を除く。)のみに適用され、第2節薬剤料は適用されない。
2 「通則2」における著しく歯科診療が困難な者の100 分の50 加算は、行動障害に対し開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に限り算定し、当該加算を算定した日における患者の治療時の状況を診療録に記載する。
3 「通則2」の加算において6歳未満の乳幼児であって著しく歯科診療が困難な者については、乳幼児に対する加算としての100 分の50 加算のみを算定する。
4 「通則4」における加算は、時間外加算等の適用される処置及び手術に伴って行われた麻酔に対して、第9部手術の時間外加算等と同様の取扱いにより算定するもので、当該処置及び手術の所定点数が150 点に満たない場合の加算は算定できない。
5 「通則4」における時間外加算等の取扱いは、初診料における場合と同様とする。
6 麻酔の休日加算、時間外加算及び深夜加算は、これらの加算を算定する緊急手術に伴い行われた麻酔についてのみ算定する。
7 その他の麻酔法の選択について、従前から具体的な規定のないものは、保険診療の原則に従い必要に応じ妥当適切な方法を選択する。
8 第10 部に規定する麻酔料以外の麻酔料の算定は医科点数表の例により算定する。この場合において、薬剤又は特定保険医療材料の使用に当たっては、医科点数表第2章11 部第3節に掲げる薬剤料及び第4節に掲げる特定保険医療材料料の例より算定する。
歯科診療報酬 麻酔のQ&A
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます