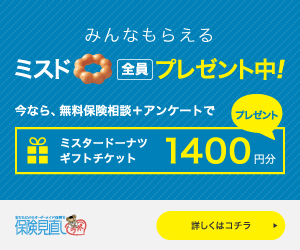第八 入院基本料等加算の施設基準等
一総合入院体制加算の施設基準
(1)総合入院体制加算1の施設基準
イ特定機能病院及び専門病院入院基本料を算定する病棟を有する病院以外の病院であること。
ロ急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ニ急性期医療に係る実績を十分有していること。
ホ当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ヘ次のいずれにも該当すること。
①地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料又は療養病棟入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
②当該保険医療機関と同一建物内に老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)又は同条第二十九項に規定する介護医療院を設置していないこと。
ト急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する入院診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
チ次のいずれかに該当すること。
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割三分以上入院させる病棟であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割二分以上入院させる病棟であること。
リ公益財団法人日本医療機能評価機構(平成七年七月二十七日に財団法人日本医療機能評価機構という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2)総合入院体制加算2の施設基準
イ(1)のイ、ハ、ヘ及びリを満たすものであること。
ロ急性期医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ急性期医療に係る実績を相当程度有していること。
ニ急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制及び実績を有していること。
ホ次のいずれかに該当すること。
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を三割一分以上入院させる病棟であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三割以上入院させる病棟であること。)
(3)総合入院体制加算3の施設基準
イ(1)のイ、ハ及びヘを満たすものであること。
ロ(2)のロを満たすものであること。
ハ急性期医療に係る実績を一定程度有していること。
ニ急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき必要な体制又は実績を有していること。
ホ次のいずれかに該当すること。
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を二割八分以上入院させる病棟であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を二割七分以上入院させる病棟であること。
一の二急性期充実体制加算の施設基準等
(1)急性期充実体制加算1の施設基準
イ一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1に限る。)を算定する病棟を有する病院であること。
ロ地域において高度かつ専門的な医療及び急性期医療を提供するにつき十分な体制が整備されていること。
ハ高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る実績を十分有していること。
ニ入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制を確保していること。
ホ感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ当該保険医療機関の敷地内において喫煙が禁止されていること。
ト公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準ずる病院であること。
(2)急性期充実体制加算2の施設基準
イ(1)のイ、ロ及びニからトまでを満たすものであること。
ロ高度かつ専門的な医療及び急性期医療に係る相当の実績を有していること。
(3)小児・周産期・精神科充実体制加算の施設基準
急性期の治療を要する小児患者、妊産婦である患者及び精神疾患を有する患者に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
(4)精神科充実体制加算の施設基準
イ急性期の治療を要する精神疾患を有する患者等に対する診療を行うにつき充実した体制が整備されていること。
ロ小児・周産期・精神科充実体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
二から五まで削除
六臨床研修病院入院診療加算の施設基準
(1)基幹型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ次のいずれにも該当する基幹型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第三条第一号に規定する基幹型臨床研修病院をいう。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ次のいずれにも該当する基幹型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)単独型又は管理型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ次のいずれにも該当する病院である単独型臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十七年厚生労働省令第百三号)第三条第一号に規定する単独型臨床研修施設をいう。)又は病院である管理型臨床研修施設(同条第二号に規定する管理型臨床研修施設をいう。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ次のいずれにも該当する単独型相当大学病院(歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、単独で又は歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第一号に規定する研修協力施設と共同して臨床研修を行う病院をいう。以下同じ。)又は管理型相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院を除く。)であって、当該臨床研修の管理を行うものをいう。以下同じ。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)協力型の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ次のいずれにも該当する協力型臨床研修病院(医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第二号に規定する協力型臨床研修病院をいう。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ次のいずれにも該当する協力型相当大学病院(医学を履修する課程を置く大学に附属する病院のうち、他の病院と共同して臨床研修を行う病院(基幹型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修医の診療録の記載について指導医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ次のいずれにも該当する病院である協力型(Ⅰ)臨床研修施設(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第三条第三号に規定する協力型(Ⅰ)臨床研修施設をいう。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ次のいずれにも該当する協力型(Ⅰ)相当大学病院(歯科医師法第十六条の二第一項に規定する歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)のうち、他の施設と共同して三月以上の臨床研修を行う病院(単独型相当大学病院及び管理型相当大学病院を除く。)をいう。)であること。
①診療録管理体制加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
②研修歯科医の診療録の記載について指導歯科医が指導及び確認をする体制がとられていること。
③その他臨床研修を行うにつき十分な体制が整備されていること。
六の二救急医療管理加算の施設基準
(1)救急医療管理加算の注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
休日又は夜間における救急医療の確保のための診療を行っていること。
(2)救急医療管理加算の注1ただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準
救急医療管理加算2を算定した患者のうち、別表第七の三の十三の状態の患者の割合が一定以上であること。
六の三超急性期脳卒中加算の施設基準等
(1)超急性期脳卒中加算の施設基準
イ次のいずれかに該当すること。
①当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
②次のいずれにも該当すること。
1当該保険医療機関(別表第六の二に掲げる地域又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第六項に規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区域に所在する保険医療機関に限る。)内に、脳卒中の診療に関する研修を受けた専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
2脳卒中の診療を行う他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ロその他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2)超急性期脳卒中加算の対象患者
脳梗塞発症後四・五時間以内である患者
六の四妊産婦緊急搬送入院加算の施設基準
妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十分な体制が整備されていること。
六の五在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定めるもの
特特掲診療料の施設基準等第三の六の(2)に該当する在宅療養支援診療所及び第四の一の(2)に該当する在宅療養支援病院
六の六在宅患者緊急入院診療加算に規定する別に厚生労働大臣が定める疾病等
別表第十三に掲げる疾病等
七診療録管理体制加算の施設基準
(1)診療録管理体制加算1
イ患者に対し診療情報の提供が現に行われていること。
ロ診療記録の全てが保管及び管理されていること。
ハ診療記録管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ニ中央病歴管理室等、診療記録管理を行うにつき適切な施設及び設備を有していること。
ホ入院患者について疾病統計及び退院時要約が適切に作成されていること。
ヘ非常時における対応につき十分な体制が整備されていること。
(2)診療録管理体制加算2
(1)のイからホまでを満たすものであること。
(3)診療録管理体制加算3
イ(1)のイ、ロ及びニを満たすものであること。
ロ診療記録管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ入院患者について疾病統計及び退院時要約が作成されていること。
七の二医師事務作業補助体制加算の施設基準
(1)医師事務作業補助体制加算1
イ医師の事務作業を補助する十分な体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
ロ勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2)医師事務作業補助体制加算2
イ医師の事務作業を補助する体制がそれぞれの加算に応じて整備されていること。
ロ(1)のロを満たすものであること。
七の三急性期看護補助体制加算の施設基準
(1)25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割以上)の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ当該病棟において、看護補助者の最小必要数の五割以上が当該保険医療機関に看護補助者として勤務している者であること。
ニ急性期医療を担う病院であること。
ホ急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ヘ急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を五分以上入院させる病棟であること。
ト看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
(2)25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者五割未満)の施設基準
(1)のイ、ロ及びニからトまでを満たすものであること。
(3)50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ(1)のロ及びニからトまでを満たすものであること。
(4)75対1急性期看護補助体制加算の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ(1)のロ及びニからトまでを満たすものであること。
(5)夜間30対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(6)夜間50対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(7)夜間100対1急性期看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
(8)夜間看護体制加算の施設基準
イ夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(9)看護補助体制充実加算1の施設基準
看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
(10)看護補助体制充実加算2の施設基準
看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
七の四看護職員夜間配置加算の施設基準
(1)看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準
イ当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十二又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ急性期医療を担う病院であること。
ハ急性期一般入院基本料又は特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料の七対一入院基本料若しくは十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ急性期一般入院料6を算定する病棟又は十対一入院基本料を算定する病棟にあっては、次のいずれかに該当すること。
①一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を六分以上入院させる病棟であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を五分以上入院させる病棟であること。
ホ看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
ヘ夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(2)看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準
(1)のイからホまでを満たすものであること。
(3)看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準
イ当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、三以上であることとする。
ロ(1)のロからヘまでを満たすものであること。
(4)看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準
イ(1)のロ及びホ並びに(3)のイを満たすものであること。
ロ急性期一般入院料2から6までのいずれかを算定する病棟であること。
八難病患者等入院診療加算に規定する疾患及び状態
別表第六に掲げる疾患及び状態
九特殊疾患入院施設管理加算の施設基準
(1)重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等を七割以上入院させている一般病棟、精神病棟又は有床診療所(一般病床に限る。以下この号において同じ。)であること。
(2)当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟又は当該有床診療所の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟又は当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟又は当該有床診療所における夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、看護職員一を含む二以上であることとする。なお、主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常)時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
(3)当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該有床診療所の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該有床診療所において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該有床診療所における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(4)当該有床診療所において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
十超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の対象患者の状態
(1)超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注1に規定する超重症の状態
イ介助によらなければ座位が保持できず、かつ、人工呼吸器を使用する等特別の医学的管理が必要な状態が六月以上又は新生児期から継続している状態であること。
ロ超重症児(者)の判定基準による判定スコアが二十五点以上であること。
(2)超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算の注2に規定する準超重症の状態
イ超重症の状態に準ずる状態であること。
ロ超重症児(者)の判定基準による判定スコアが十点以上であること。
十一削除
十二看護配置加算の施設基準
(1)地域一般入院料3、障害者施設等入院基本料の十五対一入院基本料又は結核病棟入院基本料若しくは精神病棟入院基本料の十五対一入院基本料、十八対一入院基本料若しくは二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
(2)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。
十三看護補助加算の施設基準
(1)看護補助加算1の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ看護補助者の配置基準に主として事務的業務を行う看護補助者を含む場合は、一日に事務的業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二百又はその端数を増すごとに一に相当する数以下であること。
ハ次のいずれかに該当すること。
①地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰの基準を満たす患者を四分以上入院させる病棟であること。
②診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は十三対一入院基本料を算定する病棟にあっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱの基準を満たす患者を三分以上入院させる病棟であること。
③地域一般入院料3、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ニ看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(2)看護補助加算2の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が五十又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ(1)のロ及びニを満たすものであること。
(3)看護補助加算3の施設基準
イ当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ地域一般入院基本料、十三対一入院基本料、十五対一入院基本料、十八対一入院基本料又は二十対一入院基本料を算定する病棟であること。
ハ(1)のロ及びニを満たすものであること。
(4)夜間75対1看護補助加算の施設基準
イ当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七十五又はその端数を増すごとに一に相当する数以上であること。
ロ地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2又は十三対一入院基本料を算定する病棟であること。
(5)夜間看護体制加算の施設基準
イ夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
ロ夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
(6)看護補助体制充実加算1の施設基準
看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する十分な体制が整備されていること。
(7)看護補助体制充実加算2の施設基準
看護職員及び看護補助者の業務分担及び協働に資する体制が整備されていること。
十四地域加算に係る地域
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第一項に規定する人事院規則で定める地域及び当該地域に準じる地域
十五から十七まで削除
十八離島加算に係る地域
(1)離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
(2)奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の地域
(3)小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域
(4)沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
十九重症者等療養環境特別加算の施設基準
(1)常時監視を要し、随時適切な看護及び介助を必要とする重症者等の看護を行うにつき十分な看護師等が配置されていること。
(2)個室又は二人部屋の病床であって、療養上の必要から当該重症者等を入院させるのに適したものであること。
二十療養病棟療養環境加算の施設基準
(1)療養病棟療養環境加算1の施設基準
イ長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。
ニ医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
(2)療養病棟療養環境加算2の施設基準
イ長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ロ長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
二十の二療養病棟療養環境改善加算の施設基準
(1)療養病棟療養環境改善加算1の施設基準
イ長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。
ハロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ニ医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ホ療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
(2)療養病棟療養環境改善加算2の施設基準
イ長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
ロ機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
ハ医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
ニ療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
二十一診療所療養病床療養環境加算の施設基準
(1)長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2)機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。
(3)医療法施行規則第二十一条の二第一項及び第二項に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。
二十一の二診療所療養病床療養環境改善加算の施設基準
(1)長期にわたる療養を行うにつき適切な構造設備を有していること。
(2)機能訓練室を有していること。
(3)長期にわたる療養を行うにつき十分な医師及び看護師等が配置されていること。
(4)療養環境の改善に係る計画を策定し、定期的に、改善の状況を地方厚生局長等に報告していること。
二十一の三無菌治療室管理加算の施設基準
(1)無菌治療室管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
(2)無菌治療室管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
二十一の四放射線治療病室管理加算の施設基準
(1)治療用放射性同位元素による治療の場合の施設基準
放射性同位元素による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
(2)密封小線源による治療の場合の施設基準
密封小線源による治療を行うにつき十分な設備を有していること。
二十二重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準
(1)皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を標榜している保険医療機関であること。
(2)重症皮膚潰瘍を有する入院患者について、皮膚泌尿器科若しくは皮膚科又は形成外科を担当する医師が重症皮膚潰瘍管理を行うこと。
(3)重症皮膚潰瘍管理を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
二十三緩和ケア診療加算の施設基準等
(1)緩和ケア診療加算の施設基準
イ緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ハがん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(2)緩和ケア診療加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3)緩和ケア診療加算の注2に規定する施設基準
イ一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ハ当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ニがん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(4)個別栄養食事管理加算の施設基準
イ緩和ケアを要する患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
二十三の二有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準
(1)緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)当該体制において、緩和ケアに関する経験を有する医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)及び緩和ケアに関する経験を有する看護師が配置されていること(当該保険医療機関において有床診療所緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
(3)(2)の医師又は看護師のいずれかが緩和ケアに関する研修を受けていること。
(4)当該診療所における夜間の看護職員の数が一以上であること。
二十三の三小児緩和ケア診療加算の施設基準
(1)小児緩和ケア診療加算の施設基準
イ十五歳未満の小児患者に対する緩和ケア診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該体制において、緩和ケアに関する研修を受けた医師(歯科医療を担当する保険医療機関にあっては、医師又は歯科医師)が配置されていること(当該保険医療機関において小児緩和ケア診療加算を算定する悪性腫瘍又は末期心不全の患者に対して緩和ケアを行う場合に限る。)。
ハがん診療の拠点となる病院若しくは公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれらに準ずる病院であること。
(2)小児個別栄養食事管理加算の施設基準
イ緩和ケアを要する十五歳未満の小児患者の個別栄養食事管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該体制において、緩和ケアを要する患者に対する個別栄養食事管理に係る必要な経験を有する管理栄養士が配置されていること。
二十四精神科応急入院施設管理加算の施設基準
(1)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十三条の六第一項の規定により都道府県知事が指定する精神科病院であること。
(2)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条の六第一項及び第三十四条第一項から第三項までの規定により入院する者のために必要な専用の病床を確保していること。
二十五精神病棟入院時医学管理加算の施設基準
(1)医療法施行規則第十九条第一項第一号の規定中「精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数」を「精神病床に係る病室の入院患者の数に療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数を加えた数」と読み替えた場合における同号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
(2)当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
二十五の二精神科地域移行実施加算の施設基準
(1)精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
(2)当該保険医療機関内に地域移行を推進する部門を設置し、組織的に地域移行を実施する体制が整備されていること。
(3)当該部門に専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(4)長期入院患者の退院が着実に進められている保険医療機関であること。
二十五の三精神科身体合併症管理加算の施設基準等
(1)精神科身体合併症管理加算の施設基準
イ精神科を標榜する保険医療機関である病院であること。
ロ当該病棟に専任の内科又は外科の医師が配置されていること。
ハ精神障害者であって身体合併症を有する患者の治療が行えるよう、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟であること。
(2)精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症を有する患者
別表第七の二に掲げる身体合併症を有する患者
二十五の四精神科リエゾンチーム加算の施設基準
精神疾患に係る症状の評価等の必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
二十六強度行動障害入院医療管理加算の施設基準等
(1)強度行動障害入院医療管理加算の施設基準
強度行動障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)強度行動障害入院医療管理加算の対象患者
強度行動障害スコアが十点以上かつ医療度スコアが二十四点以上の患者
二十六の二依存症入院医療管理加算の施設基準等
(1)依存症入院医療管理加算の施設基準
アルコール依存症又は薬物依存症の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)依存症入院医療管理加算の対象患者
入院治療が必要なアルコール依存症の患者又は薬物依存症の患者
二十六の三摂食障害入院医療管理加算の施設基準等
(1)摂食障害入院医療管理加算の施設基準
摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)摂食障害入院医療管理加算の対象患者
重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者
二十七がん拠点病院加算の施設基準等
(1)がん診療連携拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(2)がん診療連携拠点病院加算注1ただし書に規定する施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を一部有しているものであること。
(3)小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(4)がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。
二十七の二リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算の施設基準
(1)当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上、及び栄養管理等に資する十分な体制が整備さ)れていること。
(2)当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。
(3)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
(4)口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二十八栄養サポートチーム加算の施設基準等
(1)栄養サポートチーム加算の施設基準
イ栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ハ当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
(2)栄養サポートチーム加算の対象患者
栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者で)あって、栄養管理計画が策定されているものであること。
(3)栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(4)栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
イ一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ栄養管理に係る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ニ当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
二十九医療安全対策加算の施設基準
(1)医療安全対策加算1の施設基準
イ医療安全対策に係る研修を受けた専従の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ当該保険医療機関内に医療安全管理部門を設置し、組織的に医療安全対策を実施する体制が整備されていること。
ハ当該保険医療機関内に患者相談窓口を設置していること。
(2)医療安全対策加算2の施設基準
イ医療安全対策に係る研修を受けた専任の薬剤師、看護師等が医療安全管理者として配置されていること。
ロ(1)のロ及びハの要件を満たしていること。
(3)医療安全対策地域連携加算1の施設基準
イ医療安全対策加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ医療安全対策に関する十分な経験を有する専任の医師又は医療安全対策に関する研修を受けた専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。
ハ医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関及び医療安全対策加算2を算定する保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
(4)医療安全対策地域連携加算2の施設基準
イ医療安全対策加算2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ロ医療安全対策加算1を算定する他の保険医療機関との連携により、医療安全対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
二十九の二感染対策向上加算の施設基準等
(1)感染対策向上加算1の施設基準
イ専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師(感染防止対策に関する研修を受けたものに限る。)並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ感染防止対策につき、感染対策向上加算2又は感染対策向上加算3に係る届出を行っている保険医療機関等と連携していること。
ホ介護保険施設等又は指定障害者支援施設等と協力が可能な体制をとっていること。
ヘ他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携により感染防止対策を実施するための必要な体制が整備されていること。
ト抗菌薬を適正に使用するために必要な支援体制が整備されていること。
(2)感染対策向上加算2の施設基準
イ専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ当該部門において、感染症対策に関する十分な経験を有する医師及び感染管理に関する十分な経験を有する看護師並びに病院勤務に関する十分な経験を有する薬剤師及び臨床検査技師が適切に配置されていること。
ニ感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
ホ(1)のホを満たしていること。
(3)感染対策向上加算3の施設基準
イ専任の院内感染管理者が配置されていること。
ロ当該保険医療機関内に感染防止対策部門を設置し、組織的に感染防止対策を実施する体制が整備されていること。
ハ当該部門において、医師及び看護師が適切に配置されていること。
ニ感染防止対策につき、感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関と連携していること。
ホ(1)のホを満たしていること。
(4)指導強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算2、感染対策向上加算3又は外来感染対策向上加算に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)に対し、院内感染対策に係る助言を行うための必要な体制が整備されていること。
(5)連携強化加算の施設基準
他の保険医療機関(感染対策向上加算1に係る届出を行っている保険医療機関に限る。)との連携体制を確保していること。
(6)サーベイランス強化加算の施設基準
地域において感染防止対策に資する情報を提供する体制が整備されていること。
(7)抗菌薬適正使用体制加算の施設基準
抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。
二十九の三患者サポート体制充実加算の施設基準
(1)患者相談窓口を設置し、患者に対する支援の充実につき必要な体制が整備されていること。
(2)当該窓口に、専任の看護師、社会福祉士等が配置されていること。
二十九の四重症患者初期支援充実加算の施設基準
(1)患者サポート体制充実加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)特に重篤な患者及びその家族等に対する支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
二十九の五報告書管理体制加算の施設基準
(1)放射線科又は病理診断科を標榜する保険医療機関であること。
(2)医療安全対策加算1又は2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(3)画像診断管理加算2、3若しくは4又は病理診断管理加算1若しくは2に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(4)医療安全対策に係る研修を受けた専任の臨床検査技師又は専任の診療放射線技師等が報告書確認管理者として配置されていること。
(5)組織的な医療安全対策の実施状況の確認につき必要な体制が整備されていること。
三十褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準等
(1)褥瘡ハイリスク患者ケア加算の施設基準
イ褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた専従の看護師等が褥瘡管理者として配置されていること。
ロ褥瘡管理者が、褥瘡対策チームと連携して、あらかじめ定められた方法に基づき、個別の患者ごとに褥瘡リスクアセスメントを行っていること。
ハ褥瘡リスクアセスメントの結果を踏まえ、特に重点的な褥瘡ケアが必要と認められる患者について、主治医その他の医療従事者が共同して褥瘡の発生予防等に関する計画を個別に作成し、当該計画に基づき重点的な褥瘡ケアを継続して実施していること。
ニ褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
(2)褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(3)褥瘡ハイリスク患者ケア加算の注2に規定する施設基準
イ一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ褥瘡ケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ褥瘡の早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行うにふさわしい体制が整備されていること。
三十一ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
(1)ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
イ産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
ロ当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。
ハ公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2)ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの
三十二ハイリスク分娩等管理加算の施設基準等
(1)ハイリスク分娩管理加算の施設基準
イ当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する常勤医師が三名以上配置されていること。
ロ当該保険医療機関内に常勤の助産師が三名以上配置されていること。
ハ一年間の分娩実施件数が百二十件以上であり、かつ、その実施件数等を当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ニハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
ホ公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款に基づく補償を実施していること。
(2)地域連携分娩管理加算の施設基準
イ(1)を満たすものであること。
ロ周産期医療に関する専門の保険医療機関との連携により、分娩管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)ハイリスク分娩管理加算及び地域連携分娩管理加算の対象患者
妊産婦であって、別表第七に掲げるもの
三十三から三十三の五まで削除
三十三の六精神科救急搬送患者地域連携紹介加算の施設基準
(1)救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っている保険医療機)関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2)精神科救急搬送患者地域連携受入加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
三十三の七精神科救急搬送患者地域連携受入加算の施設基準
(1)救急患者の転院体制について、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っている保険医療機関との間であらかじめ協議を行っていること。
(2)精神科救急搬送患者地域連携紹介加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
三十四及び三十五削除
三十五の二呼吸ケアチーム加算の施設基準等
(1)呼吸ケアチーム加算の施設基準
イ人工呼吸器の離脱のために必要な診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該加算の対象患者について呼吸ケアチームによる診療計画書を作成していること。
(2)呼吸ケアチーム加算の対象患者
次のいずれにも該当する患者であること。
イ四十八時間以上継続して人工呼吸器を装着している患者であること。
ロ次のいずれかに該当する患者であること。
①人工呼吸器を装着している状態で当該加算を算定できる病棟に入院(転棟及び転床を含む。)した患者であって、当該病棟に入院した日から起算して一月以内のもの
②当該加算を算定できる病棟に入院した後に人工呼吸器を装着した患者であって、装着した日から起算して一月以内のもの
三十五の二の二術後疼痛管理チーム加算の施設基準
(1)麻酔科を標榜する保険医療機関であること。
(2)手術後の患者の疼痛管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三十五の三後発医薬品使用体制加算の施設基準
(1)後発医薬品使用体制加算1の施設基準
イ後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ当該保険医療機関において調剤した保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号。以下「薬担規則」という。)第七条の二に規定する後発医薬品(以下単に「後発医薬品」という。)のある薬担規則第七条の二に規定する新医薬品(以下「先発医薬品」という。)及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が九割以上であること。
ハ当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ医薬品の供給が不足等した場合に当該保険医療機関における治療計画等の見直しを行う等、適切に対応する体制を有していること。
ホ後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいる旨並びに二の体制に関する事項並びに医薬品の供給状況によって投与する薬剤を変更する可能性があること及び変更する場合には入院患者に十分に説明することについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ヘホの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(2)後発医薬品使用体制加算2の施設基準
イ後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が八割五分以上であること。
ハ当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ(1)のニからヘまでの要件を満たしていること。
(3)後発医薬品使用体制加算3の施設基準
イ後発医薬品の使用を促進するための体制が整備されていること。
ロ当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が七割五分以上であること。
ハ当該保険医療機関において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が五割以上であること。
ニ(1)のニからヘまでの要件を満たしていること。
三十五の三の二バイオ後続品使用体制加算
(1)バイオ後続品の使用を促進するための体制が整備されていること。
(2)直近一年間にバイオ後続品のある先発バイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先発バイオ医薬品は除く。以下「先発バイオ医薬品」という。)及びバイオ後続品の使用回数の合計が百回を超えること。
(3)当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合について、次のいずれにも該当すること。
イ次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先発バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が八割以上であること。ただし、直近一年間における当該成分の規格単位数量が五十未満の場合を除く。
①エポエチン
②リツキシマブ
③トラスツズマブ
④テリパラチド
ロ次に掲げる成分について、当該保険医療機関において調剤した先行バイオ医薬品及びバイオ後続品について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合が五割以上であること。ただし、直近一年間における当該成分の規格単位数量が五十未満の場合を除く。
①ソマトロピン
②インフリキシマブ
③エタネルセプト
④アガルシダーゼベータ
⑤ベバシズマブ
⑥インスリンリスプロ
⑦インスリンアスパルト
⑧アダリムマブ
⑨ラニビズマブ
(4)バイオ後続品の使用に積極的に取り組んでいる旨を、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(5)(4)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十五の四病棟薬剤業務実施加算の施設基準
(1)病棟薬剤業務実施加算1の施設基準
イ病棟ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ロ薬剤師が実施する病棟における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ薬剤管理指導料の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2)病棟薬剤業務実施加算2の施設基準
イ病院の一般病棟の治療室を単位として行うものであること。
ロ病棟薬剤業務実施加算1に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ハ治療室ごとに専任の薬剤師が配置されていること。
ニ薬剤師が実施する治療室における薬剤関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ホハの薬剤師を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
(3)薬剤業務向上加算の施設基準
イ免許取得直後の薬剤師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていること。
ロ都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務して地域医療に係る業務を実践的に修得する体制を整備していること。
三十五の五データ提出加算の施設基準
(1)データ提出加算1及び3の施設基準
イ診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定)一般病)棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1又は(2を満たすものであること。
ロ入院患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
(2)データ提出加算2及び4の施設基準
イ診療録管理体制加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。ただし、特定入院料(特定一般病棟入院料を除く。)のみの届出を行う保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、七の(1)又は(2)を満たすものであること。
ロ入院患者及び外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
三十五の六入退院支援加算の施設基準等
(1)入退院支援加算1に関する施設基準
イ当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配置されていること。
ホその他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)入退院支援加算2に関する施設基準
イ当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の社会福祉士が配置されていること。
ハ当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニその他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)入退院支援加算3に関する施設基準
イ当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
ロ当該部門に入退院支援、地域連携及び新生児の集中治療等に係る業務に関する十分な経験を有し、小児患者の在宅移行に関する研修を受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が一名以上配置されていること。
(4)地域連携診療計画加算の施設基準
イ当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介護サービス事業所等を記載した地域連携診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出ていること。
ロ地域連携診療計画において連携する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携診療計画の評価等を行うための機会を設けていること。
(5)入退院支援加算の注5に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(6)入退院支援加算の注5に規定する施設基準
イ一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1を除く。)を算定する病棟を有する病院(特定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7)入院時支援加算の施設基準
イ入院前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携業務を担う部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が配置されていること。
ロ地域連携を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8)入院時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ自宅等から入院する予定入院患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。
ロ入退院支援加算を算定する患者であること。
(9)総合機能評価加算の施設基準
当該保険医療機関内に、総合的な機能評価に係る研修を受けた常勤の医師若しくは歯科医師又は総合的な機能評価の経験を有する常勤の医師若しくは歯科医師が一名以上配置されていること。
(10)総合機能評価加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ入退院支援加算1又は2を算定する患者であること。
ロ介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の患者又は六十五歳以上の患者であること。
(11)入退院支援加算の注9に規定する厚生労働大臣が定める患者
イコミュニケーションにつき特別な支援を要する者又は強度行動障害を有する者であること。
ロ入退院支援加算を算定する患者であること。
三十五の六の二精神科入退院支援加算の施設基準
(1)当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
(2)当該部門に入退院支援及び地域連携に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専従の精神保健福祉士が配置されていること。
(3)当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の精神保健福祉士が、専従の精神保健福祉士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
(4)各病棟に、入退院支援及び地域連携業務に専従として従事する専任の看護師又は精神保健福祉士が配置されていること。
(5)その他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
三十五の六の三医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準等
(1)医療的ケア児(者)入院前支援加算の施設基準
医療的ケア児(者)の入院医療について、十分な実績を有していること。
(2)医療的ケア児(者)入院前支援加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める施設基準
情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)医療的ケア児(者)入院前支援加算に係る厚生労働大臣が定める患者
医療的ケアを必要とする患者であって、入院前に当該患者の療養生活環境及び処置等を確認する必要があるもの
三十五の七認知症ケア加算の施設基準等
(1)認知症ケア加算1の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)認知症ケア加算2の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき適切な体制が整備されていること。
(3)認知症ケア加算3の施設基準
当該保険医療機関において、認知症を有する患者のケアを行うにつき必要な体制が整備されていること。
(4)認知症ケア加算の対象患者
認知症又は認知症の症状を有し、日常生活を送る上で介助が必要な状態である患者
三十五の七の二せん妄ハイリスク患者ケア加算の施設基準
入院中の患者に対して、せん妄のリスク確認及びせん妄対策を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三十五の八精神疾患診療体制加算の施設基準
(1)許可病床数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(2)救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
三十五の九精神科急性期医師配置加算の施設基準
(1)通則
当該病棟において、常勤の医師は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上配置されていること。
(2)精神科急性期医師配置加算1の施設基準
イ精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ロ治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を相当程度有していること。
ハ精神科救急急性期医療入院料又は精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
ニ当該病棟に常勤の精神保健指定医(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十八条第一項の規定による指定を受けた医師をいう。以下同じ。)が二名以上配置されていること。
(3)精神科急性期医師配置加算2のイの施設基準
イ精神病棟入院基本料(十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)又は特定機能病院入院基本料を算定する精神病棟(七対一入院基本料、十対一入院基本料又は十三対一入院基本料に限る。)であること。
ロ精神障害者であって身体疾患を有する患者に対する急性期治療を行うにつき十分な体制を有する保険医療機関の精神病棟であること。
ハ許可病床(精神病床を除く。)の数が百床(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関にあっては八十床)以上の病院であること。
(4)精神科急性期医師配置加算2のロの施設基準
イ(2)のイを満たすものであること。
ロ精神科急性期治療病棟入院料1を算定する精神病棟であること。
(5)精神科急性期医師配置加算3の施設基準
イ精神科救急医療に係る実績を一定程度有していること。
ロ治療抵抗性統合失調症患者に対する入院医療に係る実績を一定程度有していること。
ハ(2)のハを満たすものであること。
三十五の十排尿自立支援加算の施設基準等
(1)排尿自立支援加算の施設基準
排尿に関するケアを行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)排尿自立支援加算の対象患者
尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害の症状を有する患者又は尿道カテーテル留置中の患者であって、尿道カテーテル抜去後に下部尿路機能障害を生ずると見込まれるもの。
三十五の十一地域医療体制確保加算の施設基準
(1)救急搬送、周産期医療又は小児救急医療に係る実績を相当程度有していること。
(2)病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
三十五の十二協力対象施設入所者入院加算の施設基準
(1)次のいずれにも該当するものであること。
イ介護老人保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホーム(以下この号において「介護保険施設等」という。)から協力医療機関として定められている保険医療機関であること。
ロ当該保険医療機関において、緊急時に当該介護保険施設等に入所している患者が入院できる病床を常に確保していること。
ハ次のいずれかに該当すること
①在宅療養支援病院又は在宅療養支援診療所であること。
②在宅療養後方支援病院であること。
③地域包括ケア病棟入院料に係る届出を行っている病棟又は病室を有する保険医療機関であること。
(2)当該介護保険施設等と平時からの連携体制を構築していること。
(3)(2)に規定する連携体制を構築していることについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
三十六地域歯科診療支援病院入院加算の施設基準
(1)地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準に係る届出を行っていること。
(2)当該地域において、歯科診療を担当する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
施設基準のQ&A
お世話になっております。栄養サポートチーム加算のチームの1人が専任から専従になった場合、算定できる患者数が増えますが、改めて届出が必要でしょうか?...
いつも大変お世話になっております。入退院支援加算1の「入院時支援加算」を届出る場合、入退院支援部門に配置した専従の看護師又は専任の看護師(病棟兼務なし)が...
看護師長の管理日勤の総夜勤を含めるのが正しいのか、含めないのが正しいのかお分かりになられればご教示いただけないでしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。