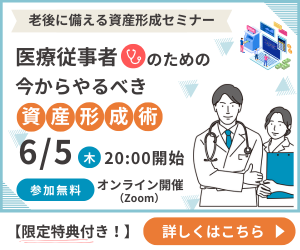下顎8番の抜歯に際して、伝麻と浸麻の併用について
下顎8番の抜歯に際して、伝麻と浸麻の併用について
- 解決済回答2
下顎8番の抜歯に際して、伝麻42+薬剤10、浸麻+薬剤10 (本数についてはどちらも適宜)が算定可能だと思いますが、この10点2つに対して理由を説明してくださいとの返戻が来ました。
伝麻と浸麻の併用については、浸麻が奏功しない場合に伝麻を使用すると記載されているものがあるのですが、歯科の場合、通常8番等には下顎孔に伝麻を使用し、抜歯する歯の粘膜下や骨膜下に注射するものとの解釈から、保険的には伝麻と浸麻を併用することはあり得ると考えますが、現場での解釈はどのようになるのでしょうか?
返戻した人がたまたまどちらもオーラ注だったのもあって、伝麻と浸麻を併用しているとわからず2本なら10×2ではなく17×1の算定にしなさいと解釈しているのかなとおもうのですが。
これが多発すると問題になるのでしょうか?
伝麻と浸麻の併用については、浸麻が奏功しない場合に伝麻を使用すると記載されているものがあるのですが、歯科の場合、通常8番等には下顎孔に伝麻を使用し、抜歯する歯の粘膜下や骨膜下に注射するものとの解釈から、保険的には伝麻と浸麻を併用することはあり得ると考えますが、現場での解釈はどのようになるのでしょうか?
返戻した人がたまたまどちらもオーラ注だったのもあって、伝麻と浸麻を併用しているとわからず2本なら10×2ではなく17×1の算定にしなさいと解釈しているのかなとおもうのですが。
これが多発すると問題になるのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答0
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。