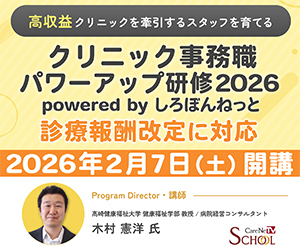再SRPしてからの再SCについて
再SRPしてからの再SCについて
- 解決済回答2
歯周検査③完了し再SRPを実施した後、翌月から(再SRPまでは不要だが、プラークの付着を認め炎症があると判断し)再SCに戻ることは可能でしょうか?ご教示の程よろしくお願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。