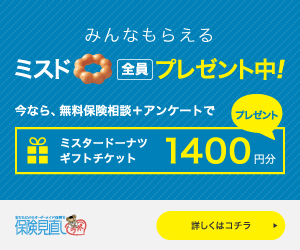訪問歯科を主体とする体制への移行と平均点数・個別指導リスクについて
訪問歯科を主体とする体制への移行と平均点数・個別指導リスクについて
- 受付中回答0
歯科診療所で事務を担当しています。 当院は現在、 ・院長(外来中心/高齢のため今後10年以内に勇退予定) ・息子の歯科医師(訪問を中心に担当) という体制で運営しています。 地域の高齢者や通院困難な方を支えるため、 息子は訪問診療に強い使命感を持っており、 今後も訪問診療を中心とした診療体制を継続していく予定です。 その一方で、訪問診療の比率が高くなるにつれて、 どうしても1日あたりの平均点数が上昇してきています。 院長としては、 「訪問が多くなると平均点数が上がるが、 それだけで個別指導の対象になるのではないか」 という不安や葛藤を抱えている状況です。 訪問歯科は地域の医療として重要であり、 誠実に取り組みたい気持ちがある一方で、 制度上の“見られ方”に対する不安もあります。 厚生局に確認したところ、 平均点数の算定方法や基準は公表していないとのことで、 訪問中心の医院がどのように扱われるのか不透明な部分があります。 そこで、ご経験のある方にご意見を伺いたく投稿しました。 【質問①】 訪問診療が多い歯科診療所では、外来主体の医院より平均点数が高くなりやすいと思いますが、 平均点数が高い“だけ”で個別指導の対象になることはあるのでしょうか? 【質問②】 訪問診療を多く行っている医院において、 個別指導で特に留意すべきポイント (通院困難の理由、訪問理由、算定の整合性、カルテ内容、同日算定など)があれば 教えていただけると助かります。 【質問③】 今後も訪問診療が増えていくため、平均点数はさらに上がると予想しています。 訪問診療を中心に運営していく上で、 “指導に備えて準備しておくべき実務的な対策” があればご教示いただけないでしょうか。 (記録、算定ルール、情報連携、院内体制など) 地域の通院困難な高齢者を支えていく体制を整えたいと考えており、 現場として適切な準備をしておきたい気持ちがあります。 多様な立場の方のご意見をいただければ幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
訪問歯科で電子カルテ(デンタルノート)記載のみで診療録として成立するか
お世話になります。 歯科医院で訪問歯科の事務を担当している者です。 現在、訪問診療時の記録をクラウド型電子カルテ (Dental...
受付中回答2
受付中回答1
解決済回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。